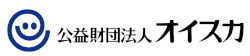フィリピン

人口 : 1億1,289万人
(2024年4月IMF推計値 日本は1億2,462万人)
一人当たりのGDP : 3,867.672US$
(2024年4月IMF試算値 日本は33,805.939US$)
森林率 : 24.11% (2020年FAO公表値 日本は68.4%)

現地スタッフからのメッセージ
2023年度は、コロナ禍の影響もなくなり、各州で緑化や環境教育が活発に進みました。活動ニーズが高まる一方、水不足や天候不順、苗木・資機材・燃料の価格高騰は活動にも深刻な影響を与えています。予算面では苦しいところも多いですが、苗木づくりから子どもたちと取り組むなど、コストを抑える工夫をしつつ、子どもたちが体験し、学ぶ機会を確保できるよう心がけています。2024 年4月には、酷暑により1万校以上の学校が閉鎖されるなど、気候変動や自然災害は深刻化していますが、だからこそ、わたしたちの活動が意味を持つと思います。今後とも活動を見守り、支えていただけると幸いです。
主な取り組み

森づくりの成果とこれから
2023年度は、12の州121の学校にて植林活動を実施。子どもたちをはじめ、教員や保護者らと、陸上で8,134本、海岸などでマングローブ5,650本を植えました。植林後の管理も生徒たちが交代しながら続けることで、苗木の多くが生存し、生長しています。彼ら自身も責任感や協調性を身に付けながら、自然に対する親しみを育んでいます。台風の被害によって活動校の校舎や植林地が被害を受けてしまうこともありましたが、倒れた木々は教室の柱や椅子、机の材料にするなど、さまざまな用途に活用することができ、災害後の復旧にも役立ちました。こうした作業には、保護者も協力を惜しまず関わってくれています。なお被害を受けた植林地では、しっかりと根を張り、防風林にもなるような樹種を中心に補植を進めています。
環境教育も活発に
環境を守る意識と力を育むための環境 教育も幅広く展開(学校菜園21校、清掃活動31校、廃棄物管理28校、環境セミナー50校)。2023年11月には、各州より代表の生徒、教員ら約100名を集めた全国ワークショップを開き、地域を超えて学びあう機会をつくりました。
2023年度植林実績:13,784本・面積 3.82ha
累計(1991年から) 植林 2,984,494本 面積 1112.24ha
2023年度に植えた主な樹種:ナラ、カシュー、マングローブなど
2023年度参加者数:14,624人
「子供の森」計画参加学校数:1,189校(1991年からの累計値)
ルソン島・アブラ州の活動»
ルソン島・ヌエバビスカヤ州、イザベラ州、ベンゲット州の活動»
ルソン島・ヌエバエシハ州の活動»
ルソン島・ケソン州、北カマリネス州の活動»
パラワン島の活動»
ビサヤス地域の活動»
ミンダナオ島・西部地域の活動»
ミンダナオ島・ダバオ地域 の活動»

2024年
7月
24日
水
2024.07 子どもたちからのメッセージ1 from フィリピン

わたしは、ダバオデオロ州のバワニ小学校に通う6年生のカッサンドラです。わたしの住んでいる地域は、農業が盛んで、 お米やトウモロコシ、根菜類などの野菜が多く栽培されています。学校では、もともと生徒会のメンバーとして、清掃活動やごみの分別に取り組んできました。毎週月曜日が学校の清掃デーです。「子供の森」計画の活動では、こうしたごみの活動をさらに頑張っていますし、ナラやモラベなど、数が少なくなってきている地域の木を植えました。活動は友だちと一緒に取り組むので、とても楽しいです。一緒にがんばろうと周りの友だちに呼びかけて、行動を促せた時はとてもうれしく思います。学校や地域での環境汚染がなくなって、きれいになってほしいです。わたし自身も、ごみを正しく分けて、ごみ箱に捨てることを習慣化していくこと、それを周りに呼びかけていくことで貢献できると思います。
2024年
7月
24日
水
2024.07 学校レポート in フィリピン

ヌエバエシハ州の農村部にある同校は、生徒たちが自然や生態系、生物多様性について学べる森を育てようと、2023年に「子供の森」計画に仲間入りをしました。校舎の裏手にある荒れた土地を整え、甘い実をつけるチコやサワーソップ、よい木材にもなるマホガニーなど、計240本の苗木を植樹。その後も交代で管理を続けた結果、植林後数か月たった今でも、ほとんどの苗木が生存していて、元の大きさの倍以上に育っている様子が確認できました。活動に参加しているフランキーくんは、「植林は少し大変だったが、自分たちが植え、手入れをした木が成長していくのを見ると、やりがいを感じる」と嬉しそうに語ってくれました。
2023年
6月
30日
金
2023.06 子どもたちからのメッセージ2 from フィリピン

マガンダンハポン(こんにちは)!
僕はパラワン島にあるイスンボ小学校のジェイです。僕たちは、神様が作った自然を守っていく必要があると思います。「子供の森」計画では、木や野菜を植える活動が楽しいです。僕の周りが自然でいっぱいになってほしいですし、野菜のような栄養のある食べ物をたくさん食べたいからです。友だちや先生、家族とも一緒に協力しながら活動しているので、特に困ることはありません。学校や地域のみんながルールを守り、助け合いながら発展してほしいです。そして、大人になったとき、僕もその一員として、社会に貢献していきたいです。
2022年
7月
20日
水
2022.7 学校レポート2 in フィリピン

学校から地域へ意識の広がり
ヌエバエシハ州に位置するこの学校は、山に囲まれた環境にあります。コロナの感染拡大を防ぐために、頻繁な外出の規制などが行われました。しかし、計画を立てながら慎重に植林活動を行うことで、ナラの木やサワーソップ、バンレイシを植えることができました。
学校の敷地の近くに木を植えることで、食料を新たに得ることができたり、地域の人たちに環境について意識してもらうきっかけにもなりました。ジャイラ先生は、「木を植えることで子どもたち一人ひとりの環境に対する責任感を育むことができると感じています。コロナ禍にも関わらず、このような植林の機会を作ってくださり、ありがとうございます」と話してくださいました。
2022年
7月
20日
水
2022.7 子どもたちの学校生活3 in フィリピン

マガンダンハポン(こんにちは)!
私の学校生活を紹介します。
コロナが広まったため、レストランに行ったり、学校に行ったり、友達と遊んだりなどの通常通りの生活が出来なくなってしまいました。クラスメイトと一緒に同じ教室で勉強する方が家で課題プリントを行うよりも良いと感じるため、早く対面での授業が再開してほしいです。コロナが収まったら、近くのビーチへ旅行に行きたいです。
2022年
7月
20日
水
2022.7 子どもたちの学校生活2 in フィリピン

マガンダンハポン(こんにちは)!
私の学校生活を紹介します。
私は小学校6年生のバレッテです。以前は毎日学校に行って、教室で先生が話す内容について活発に議論をしていました。今は学校に行くことが出来ず、課題を使って勉強をしています。自分一人ではわからない問題もあるので、そのときは両親に質問しています。先生はコロナ禍でも私たちが勉強できるように、必要なものを一生懸命準備してくれています。コロナが収まったら、学校に行ったり、友だちと遊んだり、川や山に探検に行ったりしたいです。
2022年
7月
20日
水
2022.7 学校レポート3 in フィリピン

マングローブ林が水を浄化
この学校は海岸の近くに位置しており、主な活動としてマングローブ植林を行っています。コロナ禍でも積極的に活動を行い、植林活動だけではなく、保護者へのオリエンテーションや海岸の清掃活動も行いました。マングローブは密に根を張るため、土壌を保持し、川への土壌流出を防ぐことができます。
さらに、6年生のレジ―セルナさんは、「マングローブを植える前と比べると、水質が全く異なります。マングローブによって水が浄化されるのだということを肌で感じました。マングローブは水に含まれている”不純物”を使用して成長したり、蓄えたりしてくれるそうです。きれいな水は地域全体の役に立っています。」と、マングローブによって水質も向上したというお話もしてくれました。
2022年
6月
29日
水
2022.6 学校レポート1 in フィリピン

集まる人数を工夫して実施
北カマリネス州カパロンガに位置するマビニ小学校は、山の中腹にあり、近くには水路が流れています。この地域の主な産業は農業で、多くの人々が農業で生計を立てて暮らしています。のどかなこの地域でも、コロナ禍により年間通じて対面授業が停止されたため、課題プリントによる自宅学習が続きました。教員が定期的に家庭訪問を行い、学習サポートを行いましたが、やはり分からないところをすぐに教えてもらえないため、つまづいてしまう子どもたちが多かったようです。
学校での活動は限定的になりましたが、それでも教員や周辺に住む子どもたちが中心となって植林活動を行い、植えた後の苗木の管理も続けました。また、学校に集まれない子どもたちに対しては、家庭での環境学習の機会として、苗木や野菜の種苗を配布。教員らと連携しながら植栽後の管理についてもサポートを行いました。2020年からの2年間はやむを得ず参加人数が少なくなってしまいましたが、今後行政のガイドラインに従いつつ、徐々に回復できればと思っています。
2022年
6月
29日
水
活動のあゆみとこれから in フィリピン

地元に認められ拡がる取り組み
1991年に「子供の森」計画が産声をあげたフィリピンでは、翌92年より同国政府とCFP実施に関する基本協約を締結。以降も5年ごとに更新し、関係を密にしながら活動を推進してきました。現在は、環境天然資源省、農業省、教育省など3省1局との間で締結しており、環境教育のみならず持続可能な地域づくりへの貢献も期待されています。また、アブラ州では、これまでの取り組みやスタッフの貢献が政府や教 育機関から高く評価され、 同州環境天然資源省と覚書を締結。技術的なサポートと苗木の提供を受けられるようになるなど、 地方においても政府との連携が進んでいます。
2022年
6月
29日
水
2022.6 子どもたちの学校生活1 in フィリピン

マガンダンハポン(こんにちは)!
私の学校生活を紹介します。
南イロコス州カブガオに住んでいるレジーです。学校は海のすぐそばにあります。私のふるさとの自慢は、色々な種類の野菜があることと、皆とてもフレンドリーなことです。自然が好きなので、「子供の森」計画の植林活動は楽しみの一つです。2021年にはマ ングローブの植林や浜辺の清掃活動にも参加しました。コロナ禍でずっと学校に行けず、おうちで勉強しなければならなかったので、久しぶりに友だちと一緒に外で活動できていつも以上に楽し かったです。学校が始まったら、ごみの分別も頑張りたいです。
2022年
1月
18日
火
2021年台風18号被害支援活動

2021年10月10日から11日にかけて、大型台風18号がフィリピン・ルソン島を直撃しました。各地で大雨による土砂災害、また広い範囲で洪水が発生し、40名を超える尊い命が奪われたほか、多くの家屋が倒壊・浸水被害を受けるなど甚大な被害をもたらしました。また、政府の報告によると、6万人以上の農家が被害を受けたとされています。
2021年
6月
03日
木
2021.6 Philipinnes

ステイホームでも可能な
環境教育を推進
北カマリネス州にあるルクバナン小学校は、山々に囲まれた谷間に位置する学校です。2020年度は、コロナ禍で対面授業が停止されたため、「子供の森」計画の活動も、感染対策支援や教育支援を行いながら、例年とは違う形で進めました。植林活動は、近隣の子どもたちと小規模で行ったほか、家庭での植栽も推進またSNSやウェビナーなどを通じて、感染対策や家庭でもできる環境保全を呼びかけました。5年生のレディフランセーヌさんは、「ウェビナーに参加して、環境のことだけでなく、感染予防など多くのことを学びました。花や野菜を育てる方法も学んだので、家族と一緒に栽培を始めました。パンデミックの中でも環境に貢献できることを嬉しく思います」と語ってくれました。再び皆で楽しく活動できる日を心待ちにしながら、それぞれができることに取り組んでいます。
2021年
6月
01日
火
パンデミックと「子供の森」計画 inフィリピン

懸命に学ぶ子どもたちの
在宅学習を支援
フィリピンでは、感染拡大を防ぐため、2020年3月以降、全国的に学校が閉鎖。10月5日に再開されましたが、対面式の授業は見送られ、2021年5月現在も在宅学習が続いています。活動校の多くは農村部にあり、十分なインターネット環境がないため、多くの子どもたちは学校から出される課題プリントで勉強しています。「子供の森」計画では、132校を対象に、各校のニーズに合わせ、コピー用紙やインク、中 古プリンターなど、課題づくりに必要な資材支援を行い、厳しい環境でも懸命に学ぶ 子どもたち、そして膨大な課題づくりに奮闘する教師を支えました。
2020年
6月
03日
水
2020.6 Philippines-1

海に恩返しをするために
ダルダラット小学校は、ルソン島北部・南イロコス州の海辺にある学校です。海に近いということもあり、地域住民の多くは海に関連した仕事を生業としています。多くの恩恵をもたらしてくれる海に恩返しをするため、この学校では、2004年から海岸でのマングローブ植林にも取り組んできました。
2019年
12月
27日
金
2020.1 Philippines

2019 オイスカ「子供の森」計画
ナショナルワークショップin フィリピン
11月27日から30日の3日間、フィリピンのヌエバビスカヤ州にあるオイスカの活動地で、フィリピン・「子供の森」計画ワークショップが開催されました。ワークショップにはフィリピン12の州から小学生50人、中学生9人、先生24人と、オイスカ「子供の森」計画のコーディネーター19人、他ボランテイアや講師など計103人が参加し、今回のテーマである「生物多様性の保全と二酸化炭素の隔離潜在性認識」についてワークショップや植林など様々な活動を行いました。
2019年
11月
30日
土
Green Wave 2019 Report

オイスカが2008年より参画している“グリーンウェイブ”は、国連生物多様性条約事務局(SCBD)が進める取り組みで、5月22日の「国際生物多様性の日」の前後に世界中で行われています。オイスカも「子供の森」計画(以下、CFP)参加校を中心に、国内外でさまざまな活動を実施しました。
2019年
10月
18日
金
2019.10 Philippines-1

マガンダンハポン(こんにちは)!
僕の1日を紹介します
僕は、ヌエバビスカヤ州のムーロン小学校に通う、6年生のペドロで す。学校は家から近く、歩いて5分のところにあります。「子供の森」計画では、日本から来たボランティアの皆さんと一緒に植林をしたことが心に残っています。とっても楽しかったです!
2019年
7月
03日
水
2019.7 Philippines-1

海の近くで暮らしていくために
ルッガルダカウサピン小学校は、フィリピン北部のルソン島に位置しています。海岸線から300m離れたところにあり、305名の児童が通っています。潮風の影響や暑さを少しでも軽減できるように、2017年に森づくりを始めました。
2018年
6月
27日
水
子どもたちに会いに行こう!2018オイスカツアー情報

2018年のオイスカツアー情報です!
「子供の森」計画の子供たちに会える・現場が学べるツアーが各地で開催されます。
ぜひ、ご参加ください!
2018年
5月
18日
金
2018.5 Philippines-3

マガンダン ハポン(こんにちは!)
私の一日を紹介します。
私は、ヌエバビスカヤ州のマガプイ小学校に通う、マリーです。私の家の周りは、田んぼとトウモロコシの畑が広がっています。田畑には、作物を植えた後の青々とした時や収穫前の黄金色に輝く時があり、この美しい景色がとっても大好きです。この景色がずっと続くといいなあと思っています。
2018年
5月
17日
木
2018.5 Philippines-2

苗木とともに大きくなろう!
トゥグナン小学校は、ミンダナオ島のダバオ地方、コンポステラ・バレー州にある全校児童79名の小さな小学校です。周辺の道路は舗装されておらず、車で入ることができないため、学校へたどり着くためには、3時間ほど歩いていかなければなりません。オイスカのコーディネーターたちも学校へ行くまでが一苦労ですが、無邪気な子どもたちが笑顔で迎えてくれるため、そんな疲れも吹き飛んでしまいます。
2018年
5月
17日
木
2018.5 Philippines-1

多様性の豊かさに気付く
きっかけに
キッマラバ小学校は、2008年から「子供の森」計画に参加しており、校庭には子どもたちが植えたさまざまな果樹が実っています。2017年度は、郷土樹種を中心に100本の苗木を植え、今でも子どもたちが大切に管理を続けています。また、不要になったものを材料にして行ったリサイクル工作では、子どもたちは大熱狂。貴重な資源を守ることの大切さを楽しみながら勉強できました。
2017年
4月
17日
月
2017.4 Philippine 3

マガンダン ハポン!(こんにちは)
私の一日を紹介します。
私はキャビディアナン小学校に通うチェリーです。私のふるさとの良いところは、ゴミがほとんどなく道が綺麗なところや、誰が訪れても優しくして仲良くなれるところです。でも最近は、地域の木が勝手に切られることが多くなってきたので、悲しいです。環境に優しいままの地域であって欲しいと思います。そのためにも「子供の森」計画の活動を頑張りたいです。将来は、学校の先生として自然を守り、誰にでも優しくできる子どもたちを育てるような人になりたいです。
2017年
4月
17日
月
2017.4 Philippine 2

「子供の森」計画に仲間入りしました!
ササ小学校は、フィリピン南部ミンダナオ島南東部に位置するコンポステラバレー州にある学校です。子どもたちが良い環境で勉強や遊びができるように、また涼しくて気持ちのいい空気が流れるようにとの願いを込めて、2016年に「子供の森」計画活動を始めました。
9歳のライカさんは「環境のことを教えてくれてありがとうございます。木を植えることは土砂崩れや洪水から人の命を守るものことにつながると知りました。
2017年
4月
17日
月
2017.4 Philippine 1

想像力を豊かにするリサイクル活動
マラナン小学校は、フィリピンの南西部に位置するパラワン島にある学校です。幹線道路沿いにありますが、すぐそばにはきれいな海が広がっています。1997年から「子供の森」計画に参加している同校の周りには、子どもたちが植えた木々が大きく育っています。この地域では、大雨の際に川が氾濫して洪水が起こることがありますが、木々が育つことで、そうした災害の被害が軽減されたという嬉しい報告も聞かれるようになりました。
2016年
8月
04日
木
2016.8 Philippines-3

マガンダン ハポン!(こんにちは!)
私の一日を紹介します。
私は、サンジュアンセントラル学校で「子供の森」計画に参加している5年生のエンジェル・スィリル・リヴァダです。友人からはリルと呼ばれています。学校は、家から歩いて45分のところにあり、時々はトライシクル(三輪タクシー)に乗って通っています。私のふるさとは、たばこや様々な種類の野菜の栽培が盛んです。私の好きな活動は、植林活動とエコキャンプです。これからも多くの木を植えて、水の豊かなふるさとにしていきたいです。
2016年
8月
04日
木
2016.8 Philippines-2

ふるさとの美しい海を守るため・・・
イスンボ小学校は、海岸から2~3キロ離れたところにある学校で、378人の子どもたちが通っています。学校に通っている子どもたちの多くは、パラワン島の部族の子どもたちですが、キリスト教徒とイスラム教徒の子どもたちも通っています。子どもたちが環境を守る意識を育めるよう、2011年に「子供の森」計画に参加しました。
2016年
6月
22日
水
2016.8 Philippines-1

長年の活動が目に見える成果に!
ビスタヒル小学校は、ブエナビスタ山の麓に位置する学校で、230名の子どもたちが通っています。子どもたちと地域住民にもっと環境問題に関する知識と関心を持ってもらうために、今から20年以上前の1993年に「子供の森」計画に参加しました。当時の校長先生も、実体験を通じて学ぶことが一番の教育だと信じ、活動に協力しました。活動を始める前、学校の周囲は全く木が無く、草原でしたが、子どもたちや地域住民の努力して植林活動や管理活動を続けたことで、少しずつ森が育ってきました。
2016年
6月
22日
水
2016.7 CFP Ambassadors

パプアニューギニアとフィリピンで森づくり活動に参加する子どもたちが来日!
「自分たちの国の環境を守りたい」、そんな思いで日々活動に取り組む現地の子どもたちが、各国の環境問題や自分たちが参加している森づくり活動の様子を直接報告します。
また、発表の後には、子どもたちと一緒に、グループになってそれぞれの国や地域、そして地球の環境問題や未来やについて考えるワークショップを行います♪海外の子どもたちから直接現地の様子を聞くことができ、またワイワイと仲良くなれるチャンスです☆国際協力に関心のある方、海外の子どもたちと交流したい方など皆さまのご参加お待ちしています!
2016年
6月
21日
火
2016.07 CFP Goodwill Ambassadors

6月30日~7月9日、今年度初となる「子供の森」計画(以下、CFP)子ども親善大使交流事業を行い、パプアニューギニアとフィリピンから子どもたちを招聘しました(愛・地球博成果継承発展助成事業)。フィリピンからは、ジャスティンくん(13歳)、クリスくん(13歳)、アイリッシュさん(12歳)の3名が、パプアニューギニアからは、パトリックくん(14歳)、ジャーナイくん(14歳)の2名がそれぞれ子ども親善大使として来日。東京のほか埼玉、千葉、神奈川、茨城の各県を訪問し、日本の企業や学校が取り組む環境保全や、各地で守り継がれている伝統文化について視察し理解を深めました。
2015年
6月
10日
水
2015.6 Philippines

大切な自然をみんなで育む
ブマカット小学校では植林だけでなく、「植物をどのようにして育てるか」、という実験も行っています。このような経験を通して、若い世代が自然に感謝でき、自然の恩恵も知ることができるようになります。木を植えるときに、先生たちはどうやって植物が成長していくのか、そしてどうしたら植物をもっと健康に、強く育てることができるかを教えているのです。
2015年
5月
01日
金
2015.5 Philippines-3

Magandan hapon(マガンダン ハポン)!
こんにちは! 私の一日を紹介します。
私は、ブオン小学校で「子供の森」計画に参加している1年生のウェッカ メア フランシスコ バカリアです。友達からは、アベゲイルと呼ばれています。
2015年
5月
01日
金
2015.5 Philippines-2

豊かな学校づくりを目指して
ベラスコ小学校は、1ヘクタール以上の敷地を持っており、植林活動や小さな森をつくることに適していました。この土地を生かすこと、友達と一緒に取り組む力を育てること、そして他の学校や地域などとの社会的な交流を育むことを目指して2013年7月から「子供の森」計画に参加しました。初めての活動では、マホガニーやジェミリーナなどの苗木を植えました。干ばつや気温の変化などに強く、都市地域でも育つことのできる樹種などの勉強も行っています。
2015年
5月
01日
金
2015.5 Philippines-1

みんなに優しい農業を学ぼう!
フィリピン
マナイレ小学校は、周辺の村々の水源地となる山のふもとに位置しています。学校は、周辺地域が開発されていくにあたり、環境保全活動に関して大きな関心を持っており、「子供の森」計画が子どもや両親へのよい啓発の機会となることを期待して、活動を始めました。学校の裏手には、小さな森や野菜農園、薬草農園があります。「子供の森」計画の活動では、マホガニーやマンゴーの木の植林に加え、苗
木づくりや有機肥料づくりにも取り組みました。自然素材を使って子どもたちが作
った有機肥料は、生き物や環境、そして人間の健康にとっても優しく、いい影響を
もたらしています。
2015年
2月
05日
木
2015.2 Philippines

フィリピン全土から子どもたちが参加!
ナショナルワークショップ2015
2015年1月15~17日、フィリピンのヌエバビスカヤ州において、「子供の森」計画ナショナルワークショップ2015が開催されました!ワークショップには、フィリピン全土から、「子供の森」計画に参加している子どもたちや学校の先生、コーディネーターなど総勢105名が参加。「コミュニティにおける変化のきっかけになろう:21世紀のスキルと若者たち」をテーマに、コーディネーターや専門家による講義に加え、自然観察や環境ポスター製作、ネイチャーゲームなど参加者が主体的に参加できるプログラムが実施されました。
2014年
6月
04日
水
2014.05 GEOC report

インド、フィリピンの子どもたちが来日!「子供の森」計画活動報告会を行いました@国連大学GEOC
2014 年5月23日(金)、国連大学GEOC(地球環境パートナーシッププラザ)において、”自然災害と子どもたちの挑戦「私たちの森が村を守った」~フィリピン台風30号被害と世界各地の植林活動の減災効果~をタイトルに報告会を開催しました。当日は「子供の森」計画(以下、CFP)に参加して いるフィリピンとインドの子どもたちが来日し、自らの言葉で活動を報告しました。
2014年
4月
16日
水
2014.4 Philippines-3

Magandan hapon(マガンダン ハポン)!こんにちは 僕の一日を紹介します。
僕の名前は、ローランスでみんなからはレンツと呼ばれています。ルソン島東部のケソン州にあるサリアヤ・イースト・セントラル小学校の3年生です。
2014年
4月
16日
水
2014.4 Philippines-2

『ようこそ!「子供の森」計画へ』
~2013年度新規参加校紹介~
2013年から「子供の森」計画に参加したサンタクルス小学校は、首都マニラから286キロ、州都のバヨンボンから約24キロ離れた所に位置しています。活動がはじまったきっかけは、校長先生が「子供の森」計画の参加校を視察したこと。「子供の森」計画で育てた豊かな「森」に刺激を受けた校長先生から、コーディネーターに指導の依頼があり活動が始まりました。
2014年
4月
16日
水
2014.4 Philippines-1

『森づくりに、野菜作りに、マルチに活動中!』
2000年から活動を続けるバンケロン小学校では、子どもたちだけでなく、先生や家族も一緒になって積極的に、「子供の森」計画の活動に取り組んでいます。学校は高速道路沿いに位置し、近くには川が流れています。活動では植林に加えて野菜作りや環境に関するセミナーやワークショップを実施しています。「子供の森」計画のコーディネーターが定期的に学校を訪問・指導した結果、子どもたちや、先生、また地域の人々が協力して植林に力を入れる体制ができ、学校には木陰やきれいな空気をもたらしてくれる小さな森ができました。
2013年
6月
20日
木
2013.6 Philippines

『自分たちで苗木を作ろう!』
フィリピン・アブラ
学校は休みに入っていますが、子どもたちは環境について勉強したいとフィリピンのアブラ研修センターに集まってきました。
2013年
6月
19日
水
2013.5 CFP program in Japan (PH)

「九州でフィリピン子ども親善大使交流事業を行いました!」
昨年に引き続き、今年も「子供の森」計画(以下CFP)子ども親善大使プログラムを実施することが決定。その第一弾として5月20日~27日、フィリピンより子どもたちの代表4名と学校の教員、コーディネーター各1名が来日し、福岡・佐賀にて交流事業を行いました。
1週間のプログラムの中で、子どもたちは親善大使として小学校や高校等で活動報告や交流プログラムなどを行い、また県庁や教育委員会などを表敬訪問しました。
2013年
6月
18日
火
2013.3 Philippines-12
『17年前に植えたマホガニーの活用』
フィリピン・ルソン島-ケソン州
ママラ小学校は、1995年から「子供の森」計画に参加しています。活動を始める前は空き地が広がり、強い風を防ぎ新鮮な空気を与えてくれる樹木はありませんでした。1995年7月、「子供の森」計画のコーディネーターとともに500本のマホガニーの苗木を植えました。その約半分が元気に育ち、翌年もいろいろな樹種をたくさん植えることができました。現在学校は自分たちで育てた森に囲まれ子どもたちは楽しい毎日を送っています。
2013年
6月
17日
月
2013.3 Philippines-11
『「子供の森」コーディネーターのノラ』
フィリピン・ケソン州
「子供の森」計画(以下CFP)コーディネーターのノラは、技能研修のため日本に行くことになった夫に代わり、その役を務めることになりました。ノラは1994年にCFPの活動に参加して以来オイスカ・ルクバン研修センターでボランティアスタッフとして勤務しています。
2013年
6月
17日
月
2013.3 Philippines-10

『森づくりスタート!』
フィリピン・ミンダナオ地域
ニューシボンガ高校は、教育熱心な地元の人たちの尽力で2007年に作られた新しい高校です。 2012年、この新しい学校が「子供の森」計画に加わりました。
2013年
6月
13日
木
2013.3 Philippines-8

『ふるさと再生にむけて』
フィリピン・ミンダナオ島西部地域
かつて、反政府勢力の活動が盛んだったミンダナオ。最近フィリピン政府と反政府勢力とが和平に合意し、平和への道筋がつけられました。2012年に新しく「子供の森」計画に加わったサンタ・フェ小学校がある村は、以前に反政府勢力の攻撃を受け、住民の多くが村を去り、学校も閉鎖されていました。しかし近年、情勢が安定するにつれて住民が戻り、子どもたちも再び学校に通えるようになりました。そこで、オイスカのミンダナオ・エコテック研修センターの卒業生で、現在近くの学校で校長先生をしているサムヤグさんがサンタ・フェ小学校と調整し、「子供の森」計画に参加することになりました。
2013年
6月
13日
木
2013.3 Philippines-6

『隣州の学校で出張植林』
フィリピン・ヌエバビスカヤ州
この学校が建つ地域は、かつてはヌエバエシハ州の一部でしたが、州境の改定により隣のヌエバビスカヤ州に吸収されました。今回、学校側から「子供の森」計画に参加したいとの要望を受けましたが、ヌエバビスカヤ州のオイスカの拠点からは遠いためにヌエバエシハ州の「子供の森」計画の一部として活動を始めました。
12月15日、初めての活動の日。クリスマスシーズンだったため、まずは全員でプレゼント交換をしてから、植林を行いました。生徒35名、父兄30名が参加し、学校の敷地内と、近くを流れる川沿いに100本の苗木を植えました。この川は、ヌエバエシハ州最大規模のパンタバンガン・ダムに流れ込んでおり、水源となる流域の緑化は重要な課題です。
2013年
6月
05日
水
2013.3 Philippines-5

『新しい学校でのワークショップ』
フィリピン・ヌエバエシハ
2012年に新たに「子供の森」計画に参加したこの学校で、9月末、数校が集まってワークキャンプが行われました。「未来のために緑を守ろう」をテーマとしたこのワークキャンプでは、さまざまな角度から環境保全について考えるため、紙のリサイクル、盆栽作り、ミミズ堆肥作り、環境保全のポスター作成などが行われました。
紙のリサイクルでは、使用済みの紙を使って植木鉢を作りました。まず紙を小さくちぎって水と混ぜ、粘土のようになるまでこねます。それをセメントと混ぜて型に入れ、乾かしたら出来上がり。仕上げに絵の具で色を塗り、カラフルな植木鉢ができました。