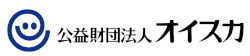タイ

人口 : 7,018万人
(2024年4月IMF推計値 日本は1億2,462万人)
一人当たりのGDP : 7,337.194US$
(2024年4月IMF試算値 日本は33,805.939US$)
森林率 : 38.9% (2020年FAO公表値 日本は68.4%)

現地スタッフからのメッセージ
環境保全に向けて地域で協働する意識を育むには、粘り強く地道な活動が必要です。その基礎をつくるのが「子供の森」計画です。植える木の数ではなく、子どもたちが活動の意義を理解し、主体的に関わること、そこに地域を巻き込んで理解や協力の輪を拡げていくことを大切にしています。将来にわたり環境を守る人を育てること、そしてその受け皿であるコミュニティを強化すること、これは車の両輪のように大事な要素です。この成果は長い時間をかけてじわじわと醸成されていくものです。 皆さまの息の長いご支援が、やがて確かな未来を形づくります。引き続きご協力をよろしくお願いします。
主な取り組み
気候変動にも負けない森づくり
2023年度は、天候不順によって計画通りに活動を行うことが難しく、臨機応変に対応、対策をしながら植林を進める一年となりました。度重なる変更に対して学校や地域も柔軟に対応してくれたことから、11の学校、3つの村、1つの寺院で計3,978本の植林活動を行うことができました。苗木を配布して、親子で村内や自宅近くに植林するというコロナ禍から始めた取り組みも継続。こうした地域の協力的な態度も活動への理解が深まってきた表れと言えます。 乾期が長引き水不足が懸念される中、ニーズが高い学校には灌漑システムも設置しました。子どもたちや教員、近隣の住民が定期的に管理作業を続けてくれ、乾燥が厳しいスリン県でも70%の生存率を保っています。

自然と共に暮らす豊かさを知る
子どもたちの環境に対する意識と知識を高めるため、ごみの分別・リサイクル活動のほか、農薬や化学肥料を使わない野菜づくり、環境キャンプ、自然観察など、体験型のプログラムを多く展開。学校の敷地に育てた森の中でも果物やキノコ類が採れるようになり、畑で育てた野菜とともに給食に活用され、子 どもたちのお腹を満たしています。
2023年度植林実績:3,978本・面積2.4ha
累計(1992年から) 植林688,672本 面積449.76ha
2023年度に植えた主な樹種:チーク、ヤーン、マンゴーなど
2023年度参加者数:3,354人
「子供の森」計画参加学校数:235校(1992年からの累計値)

2024年
7月
24日
水
2024.07 子どもからのメッセージ4 from タイ

「子供の森」計画でぼくが初めて参加をしたのは、お寺に木を植える活動でした。また、オイスカのスタッフから、苗木のつくり方を教わって、自分でつくったタマリンドの苗木を家で植えました。「子供の森」計画では、植林や木のお世話が楽しいです。友だちと一緒に活動ができ、いろんなことを学べるからです。大変なことは、手で木を植えることです。土が硬くて手が痛かったのと、 爪が黒くなりました。環境を守るというのは、日常生活の中でもできます。例えば、電気と水を節約する、植物を折って遊ばない、お菓子の袋をポイ捨てしない、蟻や小さい虫をいじめないなどです。僕は木や花を植えて、ごみもポイ捨てしないできちんと分別します。学校の緑を増やしてみんなが楽しく勉強することができるようにしたいと思います。また村の大人たちにも協力してほしいです。みんなで一緒にきれいな学校や村にしていきたいです。
2024年
7月
24日
水
2024.07 学校レポート4 in タイ

タイ東北部スリン県にあるこの学校では、積極的に植林地の管理を続けてきた結果、土壌が悪い場所でも木々が順調に生長しています。地域の環境に適した、ヤーングナー、マンゴーなどを植えました。担当のウッティポン先生は、「子どもたちは植林地が森の姿へと少しずつ変わっていく様子を見ながら水やりや、補植等に取り組んでいます。森の役割を知り、自分たちのふるさとのためにも森を守ろうという気持ちが育っているようです」と語ってくれました。学校に育った小さな森の中では、キノコも数種類採れるようになっており、自然の恵みを子どもたちに届けています。
2023年
10月
16日
月
タイから「子供の森」親善大使が来日しました!

9月20日から9月28日までの9日間、タイ・チェンライ県にて「子供の森」計画に参加する子どもたちの代表とスタッフを子ども親善大使として日本に招聘。東京・岐阜・愛知で交流事業を行いました。親善大使は、現地での活動を支援していただいている企業を訪問して、現地の環境課題や、その解決のために取り組む植林活動などについての報告を行ったほか、小学校や森林学習センターなどを訪問。各地で交流を育みながら、日本の環境保全の取り組み(ゴミの分別や森林保全など)についても学びを深めました。親善大使たちは、今後のふるさとの活動についても高いモチベーションを持って帰国したようです。今後の小さなリーダーたちの活躍にも期待が高まります。
2023年
7月
31日
月
2023.07 子どもたちからのメッセージ2 from タイ

サワディカー(こんにちは)!
ぼくはスリン県の学校に通う小学1年生のウィンです。ぼくの身の回りには、木、田んぼ、森などの自然がありますが、「子供の森」計画に参加することで、初めて自然を守る活動に参加しました。活動のなかでは、いとこと一緒に水やりをするのが一番楽しいです。これからも植えた木が大きくなるようにお世話をがんばりたいです。たくさんの木を植えて森を育てていきたいと思います。
2023年
7月
31日
月
2023.07 学校レポート2 in タイ

豊かな森を目指し管理を継続
タイ東北部スリン県にあるバーンノーントーン学校は幼稚園から小学校までの教育を実施しています。学校は村に入る道の前にあり、近くにノーントーン寺があり、そして広いサトウキビやキャッサバの畑があります。この学校では、サッカーグラウンドの周りや校舎の側など3か所で「子供の森」計画の植林を行ってきました。植林地の管理も継続しており、土壌が悪かった場所でも木が生長しています。
2022年度には植林や木々の管理、環境教育を行いました。木材になる樹種と果樹を一緒に植えて、さまざまな恵みをもたらす森をつくりたい、という学校の意向に沿い、フタバガキ科のヤーンナーや、果樹であるマンゴーやジャックフルーツなどを植えました。学校が掲げている次の目標は、植林地をしっかり管理して学校の森にすること、そして、森の恵みを活かした暮らしについて伝えていくことです。
担当のウッティポン・タウィーポン先生は、「植林地の管理作業に参加する生徒たちは植林地が森の姿へと少しずつ変わっていく様子を見ながら、水やり、施肥、補植等の作業に取り組んでいます。森が空気をきれいにすることを実感したことと、バンコクなど都会では大気汚染などが進み、人の暮らしに害が出るほど環境が悪くなっていることを知って、生徒たちが自分たちのふるさとの森を守って環境を改善しなければという思いを強くしているようです」と話をしてくれました。
2023年
7月
31日
月
2023.07 子どもたちからのメッセージ1 from タイ

サワディカー(こんにちは)!
僕はアユタヤにあるワットラムッド学校のウィンです。木を植えるときは友だちと力を合わせるので、友だちと仲が良くなり、楽しかったです。植えた木は大きかったですが、自分の手で運んで植えられて嬉しかったです(※洪水の多いアユタヤでは、その対策として比較的大きな苗木を植樹)。僕たちが自然を守らなければ、人間を含めた生き物たちが生きづらくなります。そうならないためにも、僕は学校や村の緑の面積がもっと広くなってほしいです。友だちやほかの村の人たちを誘って木を植えていきます。
2023年
7月
31日
月
2023.07 学校レポート1 in タイ

有機農業を学校の外へも広げたい
アユタヤに位置するタコ―ドーンヤーナーン学校は、入り口の前に田んぼが広がっており、田舎特有の落ち着いた雰囲気が感じられます。複数の村から子どもたちが集まる中規模の学校で、近隣住民の方々も明るく友好的です。この学校は「子供の森」計画に対して非常に協力的で、生徒たちが積極的に取り組んでいます。活動初年度である2022年は、植林に加え、有機農業の実習と環境教育活動を行いました。植林したのは、木材として使われるチークやマホガニー、果実を食べられるマンゴーやジャックフルーツなどです。 複数の樹種を植え、豊かな生態系を育むことをねらっています。次年度は、環境にも人にもやさしい有機野菜の栽培を継続し、学校を越えて村にまで有機野菜の栽培が広がるように実施していきたいと考えています。
活動を担当する先生は、『以前より学校がきれいになりました。植えた木を生徒たちがしっかり管理しており、植林や環境教育を通じて、生徒たちが森などの天然資源や環境保全に意識を向けるようになりました。さらに、生徒たちの責任感が強くなったと感じます。「子供の森」計画をきっかけとして、子どもたちには環境保全だけでなく社会貢献ができる人に成長していってほしいです。今後も学校は生徒たちの意識の向上やボランティア精神を育てるための教育活動をおこなっていきます』と意気込みを語ってくれました。
2023年
7月
31日
月
2023.07 子どもたちからのメッセージ4 from タイ

サワディーカー(こんにちは)!
ぼくはコンケン県のバーンノーンクンノイ学校のテームです。「子供の森」計画の活動に参加する前は、ゴミ拾いに参加したことはありましたが、植林はしたことがありませんでした。今回活動に参加してみて、友だちと一緒に植林するのが一番楽しかったです。また、木が大きく育っている場所では、聞いたことがない動物の声が聞けてうれしかったです。学校の森がずっとこれからも残ってほしいので、木が切られないように守っていきたいです。
2023年
7月
31日
月
2023.07 学校レポート4 in タイ

森を守る大人になってほしい
ポン学校はコンケン県ポン郡の中心部に位置する中高一貫校教育で、6.4 haの面積を持つ規模の大きな学校です。5棟の校舎とサッカーグラウンド、大きな池があり、植林地も0.96 haあります。2022年は主に植林活動を行いました。木材として活用されるチークや樹脂の取れるヤーンナー、コーヒーなど、合計500本の植林を行いました。植林前の指導、植林地の準備、植林、管理作業などすべての過程に生徒たちを巻き込んで実施しています。「子供の森」計画担当のピライポーン・ルアンルー先生は、「木が増えて学校に森ができたことが一番の変化です。また生徒たちは喜んで活動に参加しているので、植林や環境に対する生徒たちの気持ちがよい方向に向かっていると感じています。今後も、生徒たちが責任をもって植えた木を管理するよう声かけを続けます。森を守る大人に成長していってほしいです。」と語ってくれました。
2023年
7月
31日
月
2023.07 子どもたちからのメッセージ3 from タイ

サワディカー(こんにちは)!
私はチェンライ県にあるバーンパーンオイ学校3 年生のトリーティタヤーです。「子供の森」計画に参加していちばん楽しかったことは、木を植えたことです。オイスカのスタッフに教えてもらいながら、友だちと一緒に100本の苗木を植えました。準備やお世話が大変なこともありますが、「自分の木」ができて誇りに思いますし、新しいことが勉強できたこともうれしかったです。
私たちの村の近くでは、森が伐採されて畑になったり、はげ山になっているところが多くあります。活動の中では、山火事や煙の問題についても教えてもらい、山火事を防ぐための方法を勉強することもできました。これから、もっと学校や地域が木でいっぱいになってほしいです。きれいな花が咲いて、動物たちがすめるような豊かな森ができるように、みんなと一緒にたくさんの木を植えて、化学肥料や農薬を使わずに植物を育てて環境を守っていきたいです。
2023年
7月
31日
月
2023.07 学校レポート3 in タイ

森づくりの最初の一歩
タイ北部チェンライ県にあるバーンターメーウ学校は人里離れた場所にある学校で、道が悪く電気もまだ通っていません。ラーフーという山岳民族が住んでおり、農業で生計を立てていますが、生活に窮する家庭が多くあります。村の水源林や学校の近くにある森が伐採され農地にされたり、はげ山になったりしているところが多いため、「子供の森」計画の活動を通して、子どもたちに木の大切さや森林保全の必要性を伝えることを目指しています。
2022年度には、学校で食べられる果物が実るように、マレーアップル、ランブータン、アボカド、ブルーベリーなどの果樹を中心に100本の苗木を植えました。次の目標は、植林活動のほか環境保全の一環として有機農業、堆肥づくり、ゴミの処理やリサイクル、堰の設置(水の流れを管理するため)などを実施することです。
2023年
2月
15日
水
せかい!動物かんきょう会議2023 with タイ

動物の視点に立ち、身近な環境問題を考えるプログラムである「せかい動物かんきょう会議」。今年度の第1回目は、1月28日にタイと山口県の子どもたちをオンラインでつないで実施。タイからは、アユタヤ県のワットラム学校の子どもたちが参加してくれました。
参加者の自己紹介をしたあとに、まずはお互いの国についてお勉強。その後、子どもたちは身近な動物になりきり、身の回りの環境で起きている問題や、人間に気をつけてほしいことなどを発表し合いました。
2022年
8月
29日
月
学校レポート from Thailand

グリーンウェイブ活動を行いました!
タイの子どもたちがグリーンウェイブ活動の一環として、植林活動や環境教育活動に参加しました。
グリーンウェイブ活動とは、国連が定める国際生物多様性の日である5月22日を中心に、世界中の子どもたちが植樹などを行い、生物多様性を理解するきっかけをつくるための活動です。5月22日の各国現地時間午前10時に、子どもたちが植樹する木が地球上を東から西へ波のように広がっていく様子から「緑の波(グリーンウェイブ)」と名付けられました。
2022年
6月
29日
水
2022.6 子どもたちの学校生活3 in タイ

サワディカー(こんにちは)!
僕の学校生活を紹介します。
こんにちは!3年生のディーマックです。コロナで、学校で授業が受けられず、今は家で勉強しています。コロナになるのは怖いですが、いつもマスクをしなければいけないのは、大変です。でも、CFPで植林したり、家族でもヒマワリを植えたりして、楽しいこともありました。自分で木を植えたり、環境について学んだことで、自然が好きになったので、コロナが終わったら、友だちと一緒にもっとたくさんの木を植えたり、スリン県で一番大きいフラワーガーデンにも行ってみたいです。
2022年
6月
29日
水
2022.6 子どもたちの学校生活2 in タイ

サワディカー(こんにちは)!
私の学校生活を紹介します。
こんにちは。私はプラーウです。中学2年生です。学校が休みになり、いつも通りに授業が受けられなくなってしまうなど、コロナで私たちの生活も大きな影響を受けました。リモートでも授業を行っていますが、ネットワークなどオンラインの環境がない友だちもいて、みんなが同じように勉強できない状況が続いています。オンラインでの授業は家庭の負担にもなるので、早くコロナが終息し、学校で勉強できるようになってほしいと思います。
2022年
6月
29日
水
2022.6 学校レポート4 in タイ

周囲に再び豊かな自然を
パーンクラーン村、パーントンプン村、パーンアナーケート村の3つの村に接するこの学校は、周囲を森や高い山に囲まれ、山岳民族や各村の子どもたちが一緒に学んでいます。以前は、豊かな自然が見られましたが、人口の増加や農地の拡大のため木が伐られ、はげ山が進行し課題となっています。
2021年度の活動は、マスクの着用や手洗い、校内設備の消毒などコロナ感染防止策を徹底し、学校の敷地内で植林活動や環境教育を実施。ライム、マンゴー、アボカドなど食べられる実のなる樹種や、木材にもなるユカンなど、7樹種100本を植えました。植林には、学校に接する村の住民も参加し、子どもたちのみならず地域の人々の森や環境に対する意識を高める機会ともなりました。
2022年
6月
29日
水
2022.6 学校レポート3 in タイ

地域で育む森づくりの意識
バーンノーンクンノイ学校は、複数の村々に囲まれた小さな学校です。小規模ながらも、校長先生をはじめとする先生方や、村の人々の森づくりへの関心が高く、地域で協力して、子どもたちと活動に取り組んでいます。
2021年度は、新型コロナの影響を受け休校が続き、予定していた植林活動は計画通りの実施とはいきませんでしたが、一部の苗木を、生徒や地域住民へ配布。村の田畑などで植栽するなど、学校と相談の上柔軟に対応し、取り組みを継続しました。
学校や各所に植えられた樹種はパイワーンという竹で、たけのこが学校の給食になったり、販売して収入とすることもできるため、学校の希望により選定されました。現在、配布された苗木は、近隣の住民や子どもたちの手によって、管理が続けられており、学校の植栽地は学校の再開後、すぐに下草刈りを行う予定です。
子どもたちと共に地域でも森づくりを実施したことで、村の住民たちにも自然への意識が高まり、活動の輪が広がりました。
2022年
6月
29日
水
2022.6 学校レポート 2 in タイ

感染防止のため屋外で活動
アユタヤ県では、コロナ禍の影響で、この学校が唯一の活動校となりました。
生徒たちは野菜栽培の手法を学び、教室の外で楽しく活動に取り組むことができました。CFPの活動を通じて、学校の農業活動を継続することができました。
マトーハースィーナー先生は、「CFPに参加することができてとても嬉しく思っています。学校に支援してくださったオイスカの皆さんに大変感謝しております。」とCFPの活動に対して前向きな言葉を述べてくださいました。
2022年
6月
15日
水
2022.6 学校レポート1 in タイ

柵と細やかな管理で順調に生長
タイ東北部のスリン県バーンナーポー村にあるこの学校は、正面に広い田んぼが広がり、牛や水牛が闊歩するのどかな場所にあります。2019年より「子供の森」計画に参加して植林活動を行っていますが、学校のまわりには柵もあるので、家畜が侵入して、敷地内に植栽した苗木が食べられる心配もありません。子どもたちや学校の先生方の細やかな管理もあり、植栽した苗木は90%が枯れることなく生長を続けています。
しかし2021年度もコロナ禍の影響が強く、何度も長期間の休校に見舞われました。休校中は、先生方が植林地の管理を継続。子どもたちが登校できるようになったタイミングで、マホガニーやチークなど木材としても重用される5つの樹種を植栽しました。例年より遅い時期の植林とはなりましたが、学校が責任をもって雨期までしっかりと水やりなどの管理を続けるとのこと。また子どもたちのにぎやかな声や走り回る姿が見られ、学校や地域に活気が戻ってきました。
2022年
6月
15日
水
2022.6 子どもたちの学校生活1 in タイ

サワディカー(こんにちは)!
私の学校生活を紹介します。
チェンライ県にあるわたしの村は、豊かな森があり、近くには高い山もあります。ただ最近、人口が増え、農地を増やすために森が切り開かれ、はげ山も増えてきました。「子供の森」計画で植林とお世話の方法を学んだので、ふるさとの自然を守るため、今度家でも木を植えてみたいです。今は教室で勉強ができていますが、コロナ禍で、感染がある度に休校となり、勉強が遅れています。友だちとも自由に遊びに行けず、外ではマスクをつけなければいけないので、早く元のように戻ってほしいです。
2022年
6月
08日
水
活動のあゆみとこれから in タイ

地域に息づく森づくり
1992年から「子供の森」計画を推進しているタイで は、緑化が進むだけでなく、子どもたちが育てた森から小さな産業が生まれ、地域住民たちの収入向上へつな がるといった成果が生まれています。さらにこれまで築 いてきた基盤に支えられ、各地で大規模な植林プロ ジェクトが進行中。かつて活動に参加した子どもたち が、立派な青年となり、さらなる森づくりに関わり、地域の発展のために先頭にたって頑張っています。その姿から、彼らの心に森づくり、そしてふるさとの環境を守ることの大切さが刻み込まれ、 しっかりと息づいていることが感じられます。
2021年
6月
03日
木
2021.6 Thailand

学校で木を植えて、心も体も健やかに
この学校は、タイ北部チェンライ県にある山岳地域の子どもたちが多く通う学校で、保育園から小学6年生までの生徒が在籍しています。周囲は山に囲まれていますが、人口増加や農地拡大のため、はげ山化が進行し、課題となっています。コロナ禍での活動となった2020年は、感染を防ぐため、手洗いの徹底やソーシャルディスタンスの確保など、できる限りの対策をしながら植林を実施。成長が早く、大きな日影になっ たり、実が甘く、ジュースをつくることができるワーの木など郷土樹種200本を植えました。環境教育についても、状況に合わせ、学校側と内容や予定を調整しながら継続しています。このような時だからこそ、外での課外活動は、子どもたちの心身の成長の支えとなります。子どもと苗木それぞれの健やかな成長を、今後も見守り、育んでいきたいと思います。
2021年
6月
01日
火
パンデミックと「子供の森」計画 in タイ

大きな混乱なく、事業を継続
タイでは、20年3月に、新型コロナのクラスターが発生し、急速に感染が拡大。全国で非常事態宣言が言い渡され 、6月まで厳しい制限の中で生活を強いられました。自由な外出ができなかった時期は、各校と電話などで連絡を取りつつ、活動地マップを作成するなど過去のデータの整理に努めました。同年7月には学校が再開されたこともあり、学校単位の活動も徐々に戻り、他国と比較しても、大きな混乱はなく、活動できています。 年末より感染が広がり、再度休校となりましたが、1度目ほどの混乱はありません。感染予防に努めつつ、事業を運営しています。
2020年
6月
05日
金
2020.6 Thailand-8

バーンメーパッククレ学校
この学校の生徒全員が山岳民族の村から来ていて、通うには遠いため寮で生活しています。生徒たちの両親は農業を行うため、木を切って焼き畑を行っています。以前は肥沃な森がありましたが、人口や耕作地の拡大により、森林が減っているため、水不足が起きています。これらの環境問題の解決のため、生徒たちに森の大切さを理解し、大事に思ってもらえるように活動が始まりました。
2020年
6月
04日
木
2020.6 Thailand-7

バーンポーングナムローン学校
この学校に通う生徒の家庭の多くは山岳民族の貧しい家庭で、農業を生業として収入を得ています。昔は学校のまわりには豊かな森がありましたが、人口の増加や農地・住宅の拡大のため、森が破壊され、多くの水源林が失われつつあるため、水不足が生じており、活動に参加しました。
2020年
6月
04日
木
2020.6 Thailand-6

バーンナーポー学校
学校からの希望を受けて、今年度より参加校となりました。初めての活動である今年は、成長すると子どもたちを強い日差しから守ってくれるパユングやスリン県の木であるガングラオ、絶滅の危機にあるグリッサナーなど31本を植林しました。
2020年
6月
04日
木
2020.6 Thailand-5

バーンバヤーオ学校
参加から3年目を迎えた同校は森の面積が少なく、土壌も劣化しており植林には厳しい条件の土地であったが、学校や村の活動への参加希望が大変強く、活動を始めた経緯があります。活動では乾季に強いヤーングナー、成長が早く、木材としても価値の高いチークを植林しました。
2020年
6月
04日
木
2020.6 Thailand-4

コンケンウィタヤーヨンサーマッキー学校
もともとこの学校は校長先生をはじめとした先生方や地域住民の環境意識が高い一方で、学校の敷地には木が少なく、実施のサポートを必要としていました。今年から始まった活動では、乾季に強いチークやヤーングナー、果樹であるパパイヤを選定し、植林作業の準備から、植林、植えた後の管理まで、スタッフがやり方を子どもたちに伝え、一緒に行いました。
2020年
6月
04日
木
2020.6 Thailand-3

ナコンルアンウドムラットウィタヤー学校
アユタヤでは森林破壊が影響し、水不足や乾季の長期化、季節通りに雨が降らないなどの問題が目立ってきています。今年より活動に参加したナコンルアンウドムラットウィタヤー学校は、洪水にも乾季にも耐えられるヤーングナーの木を選定し植林活動を行いました。
2020年
6月
03日
水
2020.6 Thailand-2

チュンチョンポムペット学校
タイでは環境問題が国全体で抱える問題と認識され、特に人口密度の高い都市部では資源の消費率の高さや消費から排出される汚染物質が要因となり、環境問題がさらに深刻になっています。
2020年
6月
03日
水
2020.6 Thailand-1

厳しい乾燥に負けず、森を育てる
バーンノーントーング学校は、タイの東北部、ゾウで有名なスリン県にあります。この学校が位置するノントーング村では、オイスカの森林再生プロジェクトを展開しています。近い将来、地域の森を託される子どもたちが、自分たちの手でふるさとの森を守っていけるよう、同校で「子供の森」計画の活動が始まりました。
2019年
11月
30日
土
Green Wave 2019 Report

オイスカが2008年より参画している“グリーンウェイブ”は、国連生物多様性条約事務局(SCBD)が進める取り組みで、5月22日の「国際生物多様性の日」の前後に世界中で行われています。オイスカも「子供の森」計画(以下、CFP)参加校を中心に、国内外でさまざまな活動を実施しました。
2019年
5月
16日
木
2019.5 Thailand-2

サワディーカー(こんにちは)
私は、スリン県にあるバーンノーントーング学校に通う5年生のゴイです。学校には、毎朝8時に登校しています。授業が全部終わるのはお昼の3時です。
2019年
5月
16日
木
2019.5 Thailand-1

子どもたちの頑張りが少しずつ形に・・・
チェンライ県の山岳地帯に位置するこの学校は、生徒の多くがラフー族の子どもたちです。昔は、周囲に豊かな森がありましたが、人口の増加や農地の拡大のために伐採され、今でははげ山が広がっています。水源となる森が減少したことで、水不足も深刻化してきています。このような問題に対して、森を再生するだけでなく、子どもたちの中に森を大切にする気持ちを育てられるようにと「子供の森」計画に参加しました。
2018年
6月
27日
水
子どもたちに会いに行こう!2018オイスカツアー情報

2018年のオイスカツアー情報です!
「子供の森」計画の子供たちに会える・現場が学べるツアーが各地で開催されます。
ぜひ、ご参加ください!
2018年
5月
18日
金
2018.5 Thailand-3

サワディーカー(こんにちは!) 私の一日を紹介します。
私は、アユタヤにあるテーサバーンワットパーコー学校に通うアッムです。私のふるさとは、歴史があり、伝統文化がとても豊かです。学校でも、バナナの茎の芯を彫る有名な伝統工芸について学ぶ授業があります。
2018年
5月
17日
木
2018.5 Thailand-2

たのしく、おいしく学んでいます
バーンパナウ学校は、スリン県にある全校生徒84人の学校です。以前、別の学校で「子供の森」計画を担当していた先生が、校長先生として赴任。この学校でも新たに環境教育に取り組みたいとオイスカに相談したことから、活動が始まりました。
2018年
5月
17日
木
2018.5 Thailand-1

洪水からふるさとを守ろう!
テーサバーンワットパーコー学校はアユタヤ市立の学校です。川の近くに位置しているため、雨季の水量が多いときは、敷地内が浸水してしまうことがあります。こうした問題もあり、校長先生や先生たちが学校での実践指導を含めた環境教育の必要性を感じてオイスカに相談をしたことから活動が始まりました。
2017年
4月
11日
火
2017.4 Thailand 3

サワディーカー(こんにちは)
私の一日を紹介します。
私はテーサバーンチュンチョンポムペット学校に通う6年生のピモンラット・ナンタムッドです。友だちからはアッムと呼ばれています。学校には、毎日トゥクトゥク(3輪オート車)に乗って通っています。私は、2015年に「子供の森」計画親善大使として、日本へ行きました。日本の皆さんと交流してお互いについて色々と学ぶことができました。これからも、たくさんの緑を増やして、ゴミがないきれいな街をつくっていきたいです。また日本のように、ゴミはゴミ箱にきちんと捨てるように呼びかけていきたいです。
2017年
4月
11日
火
2017.4 Thailand 2

「子供の森」計画に仲間入りしました!
テーサバーンチュンチョンポムペット学校はチャオプラヤー川やアユタヤ遺跡の近くに位置し、学校に在籍する子どもたちの多くが貧しい家庭環境で育っています。そのためこの学校では植林を通じて子どもたちに環境保護への意識や知識を高め、持続可能な社会にするため資源を大切に使い、かつ長期的な目で物事を考えられるようにしたいという願いがありました。そうしたきっかけで「子供の森」計画の活動が始まりました。2016年は主に木の種類について勉強することを目的にタイ国内でも数の少ない樹種を植えました。また本校では有機農業の活動が盛んで、子どもたちは大切に有機野菜を育てています。
2017年
4月
11日
火
2017.4 Thailand 1

意識が変わると行動も変わる
バーンメーパッククレ学校は高い山々に囲まれた山岳地帯にあり、ほとんどの生徒
がラフー族という山岳民族の村から通っています。村では焼き畑農業をするために森
林伐採を行っているため、地域の森が少なくなっています。その結果、水源だった森に保水力がなくなり、水不足になるというような問題が起こっています。そのような問題に対して、子どもたちに森林と水の密接な関係を伝え、植林することの大切さを教えたいという学校の希望から、「子供の森」計画に参加することになりました。
2016年
4月
20日
水
2016.04 Thailand-3

サワディーカーสวัสดี ครับ(こんにちは)!
私の一日を紹介します。
私は、バーンノーングパム小学校で「子供の森」計画に参加している5年生のパーリチャット・チャイウォーラチットグンです。友達からはノーングパーと呼ばれています。私は山に住んでいるラフー族の出身でふるさとには豊かな森や綺麗な水があり、お店に行かなくても食べ物が周りにたくさんあります。
これからも、木がいっぱいある森づくりをしていきたいです。将来は学校の先生になって、自然を守ることやふるさとを大事にすることを教えていきたいです。
2016年
4月
20日
水
2016.04 Thailand-2

校庭の緑がどんどん広がっています
バーンノーングターカイノーングメック学校は、コンケン県にある幼稚園から中学3年までの教育が実施されている学校で、207名の生徒が在籍しています。2009年より「子供の森」計画に参加し、活動が続けられているこの学校では、植林活動への意識が非常に高く、2015年はチークの森を作りたいと、400本のチークの木を植えました。
もともと村人たちも活動に参加したいとの希望が多く、みなとても協力的です。子どもたちは、植林過程において準備作業から管理作業まで自ら実践することで、木の種類を学ぶことができるうえに、植林した苗木を育てる活動を通して、木や自然に対する関心が非常に高まってきています。
2016年
4月
20日
水
2016.04 Thailand-1

親子で学ぶ森と水のつながり
バーンノーグパム学校は町から遠く離れた山岳地域に位置し、在籍する121名の生徒の多くが山岳民族の村から通っています。生徒たちの両親の多くは農業を営んでいますが、焼畑農業の拡大により、前は学校の周りにあった豊かな森も失われていまい、そのため乾季に水が足りなくなることもしばしばです。このような状況から森と水の関係性について生徒たちに理解してもらい、そして学校で木を植えて大切に管理していくよう指導したいという先生たちの希望から「子供の森」計画に参加するようになりました。
2015年
11月
16日
月
2015.10 CFP Ambassadors

インドネシアとタイの子ども親善大使が来日しました!
10月19日~30日の日程で「子供の森」計画親善大使としてインドネシア、タイから子ども親善大使が来日しました。子どもたちは、奈良、大阪、愛知、岐阜、静岡そして東京と多くの地域を訪問し、各地で交流を育みながら、日本の自然や環境についての取組みについて学びました。 最初に訪れた大阪府では、豊能町立吉川小学校を訪問。歌や踊りなどの発表を通じて、それぞれの国の文化を紹介するとともに、日本の伝統的な遊びや絵の共同制作を通じて、言葉を超えた交流を楽しみました。22日には、おおさかATCグリーンエコプラザ(大阪市)を訪問。環境問題に対する企業の取り組みや最新技術の展示に子どもたちは興味深く話を聞いていました。
2015年
6月
08日
月
2015.6 Green Wave

今年も地球上で「緑の波」が!
今年もグリーンウェイブ(5月22日の朝10に世界各国の子供たちがいっせいに植林を行い、地球上に「緑の波」を起こそうという活動)に参加したという第一報が届きました。
今回はそれをご紹介したいと思います!
2015年
5月
07日
木
2015.5 Thailand-3

สวัสดี ครับ!(サワディーカー)
こんにちは!私の一日を紹介します。
僕は、バーンチョークタイ学校で「子供の森」計画に参加している6年生のパイブーン・スィーブンルアンです。友達からは、ダムと呼ばれています。学校は朝8時半に始まり、夕方の4時まで授業があります。僕の村の自慢は、村中にあるハーブです! 僕もハーブの効能や使い方などを勉強することが大好きです。
2015年
5月
07日
木
2015.5 Thailand-2

豊かな緑を取り戻そう
この学校は町から離れた山間部にあり、幼稚園から小学6年生までの子どもたちが学んでいます。ほとんどの子どもたちが山岳民族であるラフー族の村から来ており、子どもたちの両親は農業を行うため、木を切って焼き畑を行っています。以前は学校の周りに豊かな森がありましたが、農地の拡大で森林が減ってきたために、乾季の水不足や雨季の土砂崩れなどの問題が起きるようになってしまいました。この学校は、「子供の森」計画には1996年から参加し、その後自主的な活動に切り替わっていましたが、将来このような環境問題が深刻になることを考えて、早急に植林活動を行い森を育て守っていくために、「子供の森」計画に再び参加することを決めました。
2015年
5月
07日
木
2015.5 Thailand-1

楽しく学ぶ 自分のふるさと
バーンチョークタイ学校は生徒数が122人、教師が8人の小さな学校です。学校は村の真ん中に位置しており、校舎の裏側には村人の田んぼが広がっています。村の主な産業は稲作で、カンボジア語とタイ語が話されています。昨年の「子供の森」計画では、チークやライムの木などを地域住民とともに、協力して植林しました。また、子どもたちは自然や農業、自分の村についての理解を深めようと、ネイチャーゲームや地域の伝統的な踊り(ガントルム)、ハーブの庭作りなどに力を入れて取り組みました。
2014年
10月
22日
水
2014.9 CFP Ambassadors

タイとスリランカから
子ども親善大使が来日しました!
2014年9月4日~9月14日、「子供の森」計画」(以下、CFP)子ども親善大使招聘事業として、タイとスリランカでCFPに参加している子どもたちが来日。
岐阜、愛知、東京、千葉を訪問しました。
来日したのは、スリランカからプールニマさん(10)、アクシャヤくん(15)、タイからはオウムさん(13)とクーキックさん(15)。またCFPコーディネーターに加え、スリランカからは現地で活動を支えてくれている学校の先生も参加しました。