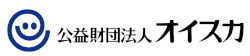各国の活動
各国で展開中の「子供の森」計画の活動をご紹介します。

2024年
12月
23日
月
2024 Greeting Card

今年も、各国の子どもたちからグリーティングカードが届きました!
身の周りの森や海、それらを守る活動など、各々が思う自然を堂々と描いてくれました。また、日本の絵や「ありがとう」の日本語が添えられており、日本のことを想像しながら一生懸命描いてくれた子どもたちの様子が頭に浮かびます。
子どもたちからのグリーティングカードは、「子供の森」計画の支援者の皆様にお送りしています。
来年このカードを受け取ってみたい!という方は、こちらをご覧ください。
2024年
12月
06日
金
2024.12 子どもからのメッセージ from モンゴル

僕は、オルホン県バヤンウンドル村にある15番学校に通っています。「子供の森」計画の活動では、オイスカの人たちに教えてもらいながら、木を植えたり、日本の小学生とオンラインで身近な環境問題や、そこに住んでいる動物の気持ちを考えるワークショップに参加しました。森がなくなると、棲み家や食べものがなくなり、たくさんの動物たちが生きていけなくなります。数がどんどん少なくなっている動物が多くいることも知りました。以前は、環境について考えたり、行動したりすることはあまりありませんでした。でも今は、すべての人や、すべての動物が、安心して住むことができる環境をつくっていくために、僕たちがするべきことはたくさんあると思います。今後は、植えた木の管理を続けながら、以前の僕のように環境についてあまり関心のない友だちや地域の人たちに学んだことを伝えていきたいです。
2024年
12月
06日
金
2024.12 学校レポートinモンゴル


モンゴル北部オルホン県のバにあるこの学校は、2022年から「子供の森」計画に参加しています。
活動2年目である2023年には、バードチェリー100本を植えました。大きくなると、春には雪のような白い花が咲き、秋には葉が黄紅色に変わるなど、季節の移り変わりを楽しむことができます。また、オイスカが地域住民と共に取り組む近隣の山での植林にも参加。カラマツ600本を植えました。子どもたちは植林後の水やりも欠かさず行っており、7年生のサンジャーダンバさんは「木を植えることができてうれしい。自分の木ができた。卒業する年になったら、自分の身長と植えた木の高さを比べてみたい」と語るなど、苗木の生長を楽しみにしている様子が伺えました。
2024年
9月
04日
水
2024.09 学校レポートinウズベキスタン

この学校はウズベキスタン・カラカルパクスタン共和国の首都ヌクスから北に56㎞ほど離れたチンバイという町にあります。周辺には、綿花や麦の畑が広がっています。記念すべき第1回目の活動では、オイスカの日本人スタッフも同行して果物やクルミの木を植えました。学校のナルギザ先生は「初めて他の国から人を招いて植林をした。子どもたちは普段はとてもシャイだが、今日は一生懸命コミュニケーションを取ろうとしていた。これからも自然を守ってほしい」と語ってくれました。今後は、植えた苗木の生長の記録や適切な管理についての学習も行う予定です。
2024年
9月
04日
水
2024.09 子どもからのメッセージ from 中国

私は、中国・内モンゴル 自治区にある阿拉善左旗蒙古族学校3年生のウユンです。学校の横には防砂林があり、その向こう には広大なゴビ砂漠が広がっています。私たちの学校では、これまでオイスカの沙漠化防止プロジェクトに協力して、沙漠での植林活動に力を入れてきました。私も友だちと一緒に、オイスカの植林地に行って、沙漠にも育つ、サクサウールという木を植えました。この木は灌木で、大きく育つものではないですが、砂が飛んでいくのを防いだり、根っこに漢方薬になる植物を寄生させて育てることができると教えてもらいました。普段は教室の中で勉強する時間が多いので、外で行う植林活動はとても楽しいです。いろいろな新しいことを勉強することもできます。木を植えると、心も元気になり、大地も緑になります。私たちが行動を続けることで、ふるさとの沙漠化が止まり、緑が広がってほしいです。
2024年
9月
04日
水
2024.09 学校レポートinパプアニューギニア

この学校は、東ニューブリテン州の中で、経済的な発展が最も遅れているポミオ郡のノギア村にあります。ノギア村では、かつて森が企業によって伐採され、荒廃してしまった経験があるため、教科書だけでなく木を植えて環境について考える経験を子どもたちにしてほしいという願いが学校理事会を通じてオイスカに届けられ、「子供の森」計画の活動が始まりました。初めての活動では、室内が暑い時、子どもたちが外で授業を受けるときの木陰をもたらすターミナリアや、おいしい果実をもたらしてくれるマンゴスチンなどの苗木200本を植えました。今後は、野菜栽培やカカオの苗木づくりも教え、家庭にも持続可能な有機農業が伝わるよう取り組みたいと考えています。
2024年
9月
04日
水
2024.09 子どもたちからのメッセージfromパプアニューギニア

ロレインさん)オイスカスタッフから忘れられない言葉を聞きました。“樹木は人類がいなくても生きていけるが、人間は樹木 が無ければ生きていけない”。樹木はとっても大切な存在ということです。樹木から酸素、食べ物、家屋、水、薪などの恵みをもらっているので、人間の命が存続できています。木の世話をして守ることは、わたしたち人間にとっても大切なことです。これからも新しい学びができることを楽しみにしています。 ケリーンさん)初めて「子供の森」計画に参加しましたが、とても興味深く、特別な機会になりました。森や母なる地球の大切さを思い起こさせてくれました。私は今までにたくさんの企業が木を伐採して、トラックに丸太を積んで運んでいくのを見てきました。パプアニューギニアには多くの種類の木があります。「子供の森」計画の活動を通じて、環境の守り方を教えてもらえたことに、感謝しています。
2024年
8月
22日
木
2024.08 学校レポートinマレーシア

この学校は、サバ州タンブナンの水源地の山にあり、校舎は斜面に建てられています。学校周辺がより緑豊かになり、子どもたちが実践を通じて環境に関する学びを深められるよう、そして保護者と学校が協力しあう機会となるよう、学校からの依頼を受けて2022年から「子供の森」計画の活動を開始しました。2023年は、子どもたちと保護者の手で、校舎の裏の斜面地にカラマンシーなどの苗木を250本植えました。同校のマウンシオン先生は「管理を続けて、苗木が順調に生長していることで学校の環境も美しくなっている。この活動のおかげで、子どもたちは自然の尊さに気づき、自然を大切にしようと努力するようになった」と話してくれました。
2024年
8月
22日
木
2024.08 子どもたちからのメッセージfromマレーシア

わたしはサバ州タンブナンにある、ラグカム小学校の6年生です。タンブナンは、世界で一番大きな花と言われるラフレシアの保護林があることで有名です。ふるさとでは農業が盛んです。とても蒸し暑い気候ですが、そのおかげで植物がよく育ちます。 わたしは新鮮できれいな空気を恵んでくれる、美しい自然が好きです。「子供の森」計画の活動では、果物の木などを植えました。植林地は斜面だったので、苗木をそこまで運ぶのが大変で、疲れました。でも、木を植えたことで学校の景色がよくなって嬉しいですし、いつか実った果物をみんなで食べるのも楽しみにしています。活動に参加して自然がくれる恵みやすばらしさに気づくことができました。これから、学校でもっとたくさんの植物や木が育ってほしいです。また、友だちや家族と環境への思いを共 有してみたいとも思っています。
2024年
8月
21日
水
2024.08 子どもからのメッセージ from スリランカ

僕はクルナワ学校8年生のクマラです。「子供の森」計画の活動では、野菜づくりがとても好きです。自然を相手にするおも しろい仕事だと思っています。種をまき、発芽して数日すると、だいたい2、4、6枚の葉がでて、少しずつ育っていきます。植物は手をかけたぶん、応えてくれます。水不足だと葉が枯れ、肥料が足りないと葉が黄色くなり、肥料をやると葉が青々としてきます。 まるで、植物たちが僕たちと会話をしているようです。ただ2023年は、長い間雨が降り、野菜にも大きな影響が出て大変でした。学校の畑は水はけが悪いため、根が腐ってしまったものも多くありました。このように困ったことがあればオイスカのスタッフに相談をしています。種やビニールポットなどをサポートしてくれるだけではなく、相談にも乗ってくれるので、心強いです。他の学校のよいモデルとなるように、これからも頑張りたいです。
2024年
8月
21日
水
2024.08 学校レポート in スリランカ

クルネ-ガラ県ポトゥハラにあるこの学校は、子どもたちが環境と村の文化について学べる機会をつくりたいという思いから、「子供の森」計画に参加。オイスカのサポートで、それまで小規模に取り組んでいた学校菜園の活動を拡大することになりました。野菜の種類に合わせて、ポットや支 柱を使った育て方を教えたり、有機肥料を使った液肥づくりのセミナーも開催。オクラ、冬瓜、大根、トウガラシ、ほうれん草、豆などを植え、収穫した野菜は学校の子どもフェアで販売しました。 保護者も興味を持ってくれており、この活動を各家庭に拡げていくことを次の目標としています。
2024年
8月
07日
水
2024.08 学校レポート1 in ミャンマー

この学校はもともと敷地内に緑がほとんどなく、保護者や校長先生の木を植えたいという思いからオイスカに要請があり、2021年に「子供の森」計画の活動を始めました。2023年には50本の木を植林し、乾燥地ながら生存率も80%を保っており、少しずつ緑が増えています。井戸もありますが、水質がよくないため、子どもたちは学校の前にある小さな池の水を利用して水やりを行っています。学校菜園も設置し、6区画に分けて野菜を育て、収穫したものは子どもたちが持って帰ることができました。参加した生徒からは「野菜がよくできたのを見て、とてもうれしい気持ちになった」 「学校菜園で勉強したことを自分の家でも頑張りたい」と前向きな感想が多く寄せられました。
2024年
8月
07日
水
2024.08 子どもたちからのメッセージ2 from ミャンマー

私は、エサジョ郡に住むノルチョーです。小学生のころから「子供の森」計画に参加しています。活動に参加する前は、あまり環境を守るということを意識したことがありませんでした。オイスカのスタッフに森の大切さを教えてもらい、植林に参加するようになりました。「子供の森」計画にはたくさんの楽しみがあります。みんなで木を植えたり、環境について勉強したり、ワークキャンプでたくさんの友だちをつくったり。一番の思い出は、子ども親善大使としてミャンマーを代表して日本に行ったことです。でも今のエサジョ郡は、情勢が悪くなって活動が難しく、人が集まることも困難です。最後にワークキャンプに参加してから長い時間が経ってしまいました。みんなが環境保全に活発に参加できるようになってほしいですし、植林したり、ごみの分別をしたり、また活動が定期的にできるようになる日が早く来ることを願っています。
2024年
7月
31日
水
2024.07 子どもからのメッセージ from インド

私は、ウッタルプラデシュ州メーラトにあるアディヤン学校の6年生です。私にとって、自然は神から与えられたかけがえのな い宝物です。たくさんのことを自然から学ぶことができます。例えば、樹木や植物たちは、無償の愛を教えてくれ、風や太陽は時間の概念を教えてくれます。小さな頃から自然が大好きだったので、家でも植物を育てていますが、そのお世話をしているときは満足感を得られます。「子供の森」計画の活動では、友だちと一緒に学校でさまざまな種類の木を植えることができました。以前よりもっと自然に親しむことができて楽しいです。私は、学校や地域で環境教育や環境意識を高めるための取り組みが続けられることを願っています。 一人ひとりが自分にも責任があることに気づき、行動していかないといけません。私も周りの人に呼びかけながら、自分でも行動していきたいです。
2024年
7月
31日
水
2024.07 学校レポート in インド

インド北部ハリヤナ州グルガオンにあるこの学校は、街の中心から離れた住宅街にあり、広い敷地を持っています。しかしその多くが、緑があまりなく乾いた荒野であったため、2006年から「子供の森」計画に参加し、植林を続けてきました。最近では、生徒自身が、低学年や地域住民に環境や植物の役割を伝える活動にも取り組んでいます。「緑の多いこの学校は周囲に比べて涼しく過ごしやすい、と生徒たちは、木々がもたらすよい恵みを身を持って感じている。活動をきっかけに、彼らの環境や社会課題に対する参加意識も変わってきた。とても感謝している」と校長先生は語ってくれました。今では「子供の森」計画のモデル校となり、他校からの見学も受け入れています。
2024年
7月
24日
水
2024.07 子どもからのメッセージ from バングラデシュ

ぼくはダッカにあるヤープール小学校の5年生です。友だちからはアリフと呼ばれています。学校の南側には、ヤープール町の中央モスクがあり、北側には、高校があります。ぼくは緑ゆたかな自然が大好きです。自然の中に大きな木々がいっぱいあったら、もっときれいだと思います。木を植えることは、美しい自然をさらによくして、守っていくための活動だと思います。だからぼくはこの活動が好きです。家でもフルーツがなる木や花が咲く木を家族と植えたことがありますが、「子供の森」計画では、さまざまな種類の木を植えることができました。友だちと一緒に楽しく活動しているので、特に困ったことや大変なことはありません。これからも活動を続けて、将来、学校やその周りが緑であふれるのを見たいです。そしていつか、オイスカや環境問題に対して同じような考えを持つ団体で働きたいと思っています。
2024年
7月
24日
水
2024.07 子どもたちからのメッセージ1 from フィリピン

わたしは、ダバオデオロ州のバワニ小学校に通う6年生のカッサンドラです。わたしの住んでいる地域は、農業が盛んで、 お米やトウモロコシ、根菜類などの野菜が多く栽培されています。学校では、もともと生徒会のメンバーとして、清掃活動やごみの分別に取り組んできました。毎週月曜日が学校の清掃デーです。「子供の森」計画の活動では、こうしたごみの活動をさらに頑張っていますし、ナラやモラベなど、数が少なくなってきている地域の木を植えました。活動は友だちと一緒に取り組むので、とても楽しいです。一緒にがんばろうと周りの友だちに呼びかけて、行動を促せた時はとてもうれしく思います。学校や地域での環境汚染がなくなって、きれいになってほしいです。わたし自身も、ごみを正しく分けて、ごみ箱に捨てることを習慣化していくこと、それを周りに呼びかけていくことで貢献できると思います。
2024年
7月
24日
水
2024.07 学校レポート in フィリピン

ヌエバエシハ州の農村部にある同校は、生徒たちが自然や生態系、生物多様性について学べる森を育てようと、2023年に「子供の森」計画に仲間入りをしました。校舎の裏手にある荒れた土地を整え、甘い実をつけるチコやサワーソップ、よい木材にもなるマホガニーなど、計240本の苗木を植樹。その後も交代で管理を続けた結果、植林後数か月たった今でも、ほとんどの苗木が生存していて、元の大きさの倍以上に育っている様子が確認できました。活動に参加しているフランキーくんは、「植林は少し大変だったが、自分たちが植え、手入れをした木が成長していくのを見ると、やりがいを感じる」と嬉しそうに語ってくれました。
2024年
7月
24日
水
2024.07 学校レポート1 in バングラデシュ

ダッカ近郊にあるこの学校は、広い敷地を持つ反面、緑が少なく、環境を改善したいという希望で、2023年より「子供の森」計画に参加。木陰をもたらし、厳しい太陽をさえぎってくれる木、景観をよくする木や子どもたちが大好きなマンゴーなど、さまざまな種類の苗木を植えました。環境保全や地球温暖化について考える講義も行ったほか、活動の一環で花壇の手入れや学校菜園にも取り組んでいます。同校のサイダ先生は「活動によって学校の環境が美しくなった。子どもたちは交代で苗木を管理しており、木を思いやる感覚も育っているようだ」と話してくれました。
2024年
7月
24日
水
2024.07 子どもからのメッセージ from フィジー

ぼくは、ノイコロ地区学校8年生のペニです。学校の近くには、川が流れていて、その冷たい水の中で泳ぐのが気持ちよくて大好きです。「子供の森」計画では植林活動などに取り組んでいますが、一番の思い出はエコキャンプに参加したことです。特に有機農業についての講義がおもしろかったです。ぼくが住んでいるところは高地で、あまり農業の経験もなかったので、「子供の 森」計画を通じて、野菜の育て方についても勉強することができました。新しい友だちもできて、一緒に母なる地球を守っていこうという気持ちも大きくなりました。学校に植林した苗木の一部は、迷い込んでしまった動物に食べられて枯れてしまいましたが、あきらめずにもう一度植えたいです。将来、学校のまわりがもっと森に囲まれて過ごしやすい環境になるように、これからももっと木や果物の木、そして野菜を育てていきたいです。
2024年
7月
24日
水
2024.07 子どもからのメッセージ4 from タイ

「子供の森」計画でぼくが初めて参加をしたのは、お寺に木を植える活動でした。また、オイスカのスタッフから、苗木のつくり方を教わって、自分でつくったタマリンドの苗木を家で植えました。「子供の森」計画では、植林や木のお世話が楽しいです。友だちと一緒に活動ができ、いろんなことを学べるからです。大変なことは、手で木を植えることです。土が硬くて手が痛かったのと、 爪が黒くなりました。環境を守るというのは、日常生活の中でもできます。例えば、電気と水を節約する、植物を折って遊ばない、お菓子の袋をポイ捨てしない、蟻や小さい虫をいじめないなどです。僕は木や花を植えて、ごみもポイ捨てしないできちんと分別します。学校の緑を増やしてみんなが楽しく勉強することができるようにしたいと思います。また村の大人たちにも協力してほしいです。みんなで一緒にきれいな学校や村にしていきたいです。
2024年
7月
24日
水
2024.07 学校レポート4 in タイ

タイ東北部スリン県にあるこの学校では、積極的に植林地の管理を続けてきた結果、土壌が悪い場所でも木々が順調に生長しています。地域の環境に適した、ヤーングナー、マンゴーなどを植えました。担当のウッティポン先生は、「子どもたちは植林地が森の姿へと少しずつ変わっていく様子を見ながら水やりや、補植等に取り組んでいます。森の役割を知り、自分たちのふるさとのためにも森を守ろうという気持ちが育っているようです」と語ってくれました。学校に育った小さな森の中では、キノコも数種類採れるようになっており、自然の恵みを子どもたちに届けています。
2024年
7月
24日
水
2024.07 学校レポート in フィジー


この学校は、ビチレブ島の山間部、島内でもっとも長いシガトカ川の源流近くにあります。1997年から「子供の森」計画に参加しており、校内にはかつて子どもたちが植えたマホガニーが大きく育ち、木陰をもたらしています。2023年度には、200本の植林を行ったほか、有機農業(上写真)や養鶏にも取り組みました。またエコキャンプ(下写真)の会場となり、同校を含む5校から代表の子どもたちが参加。校長のトマシ先生は、「2日間にわたるエコキャンプでは、体験型の学習の機会が少ない内陸部の子どもたちが、いのちのつながりについて理解を深めながら、山だけでなく、沿岸部の保全の大切さについても学ぶ貴重な機会になった」と感想を話してくれました。
2024年
7月
24日
水
2024.07 子どもからのメッセージ from カンボジア

私はコンポンチャム州に住んでいるラベア ロワー学校8年生のキムです。私は自然が大好きです。植物や森が大好きなので、学校での授業のほかに、田植えや稲の世話、稲刈りなど、両親の田んぼの手伝いをいつもしています。「子供の森」計画に参加する前は、周りがよい環境になるようにと、家の周りを掃除したり、クラスメイトと交代で教室を掃除したりと、自分なりにできることをしていました。今年初めて「子供の森」計画に参加して、近くのお寺で、地域の人も一緒になって植林することができました。コーディネーターから木の役割や植樹のやり方を教えてもらい、大好きな自然のためにできることが増えてとてもうれしく、楽しく活動をしています。将来的にはすべての学校や寺院で植林活動をしてほしいと思っています。みんなが植物を植えれば、カンボジアが緑と新鮮な空気に包まれた素晴らしい国になるに違いありません!!
2024年
7月
24日
水
2024.07 学校レポート in カンボジア

この学校はコンポンチャムの州都から約70km離れた農村部にあり、周囲にはゴム農園が広がっています。教員や児童たちの「子供の森」計画への参加を希望する声が多く、2023年から活動を始めました。初めての植林活動では、メンガやケランジィなど130本を植樹。学校のニィ・チャンティ先生は、「今まで一度も政府やほかのNGOから苗木の支援や環境保全への援助をもらうことができなかったが、今年はオイスカのサポートで植林活動を行うことができて本当にうれしい。子どもたちは、水やり当番を決めて苗木を管理し、大切に育てている。来年は学校も資金を調達して菜園活動も始めたい」と、学校に緑が順調に育っている様子と今後の意気込みを語ってくれました。
2024年
7月
18日
木
2024.07 子どもからのメッセージ from インドネシア

わたしは、スカブミ県にあるカドゥプグルイスラム小学校5年生です。小さいころから両親から身の回りの環境を大切にしなさいと教えられてきたので、家でも植物に水やりをしたり、庭を掃除したりしています。種から芽が出て、カラフルな色を見せてくれる植物を見ていると心が落ち着きます。ありがとうという気持ちになりますし、植物を傷つけたくないです。
「子供の森」計画の活動に参加してからは、木の管理の仕方やごみ処理などの新しい知識を得ることができています。時々、育てている花が枯れてしまったり、環境に無頓着な人がポイ捨てするところを見ると、悲しい気持ちになります。学校のみんなが、環境についてしっかり考えるようになって、植林をしたり、ごみのリサイクルについて取り組んでほしいです。もちろん、わたしも環境を守るための活動にこれからもどんどん参加していきたいと思っています。
2024年
7月
18日
木
2024.07 学校レポート1 in インドネシア

環境の大切さを伝える啓発活動も積極的に!
西ジャワ州スカブミ県の高地にあるこの学校は、環境への取り組みに熱心で、「子供の森」計画も、10年生に対して年間74時間の授業が割り当てられ、講義のほか植林やごみの分別などを行っています。またエコクラブが結成され、周辺の小中学校の「子供の森」計画の活動をサポートしているほか、環境パレードを行ったり、SNSでの発信も積極的です。同校のヌニ(Neni Nuraeni)さんは、「生徒たちは、マイボトルや弁当箱の持参を心がけるようになった。学校も木陰ができ、景観も美しくなっている」と意識や環境の変化を語ってくれました。
2023年
12月
29日
金
Greeting Cardが届きました!

年末年始に合わせて、今年も各国からグリーティングカードが届きました。グリーティングカードは「子供の森」計画に支援していただいている方々に、子どもたちが日ごろの感謝の気持ちを込めて書いたカードです。色鮮やかで自然豊かな絵が多く、子どもたちが自然を愛する心を育んていることが伝わります。
来年このカードを受け取ってみたい!という方は、こちらをご覧ください。
2023年
12月
11日
月
インドネシアから「子供の森」親善大使が来日しました!

11月20日~29日、インドネシアから「子供の森」計画(以下、CFP)に参加する子どもたちとスタッフの代表が来日し、福岡、佐賀、山梨、東京を訪問しました。一行は、海岸林の保全に取り組む学校を訪れ、互いに活動報告を行ったり、オイスカが企業や行政などと協働して取り組む森づくりの現場の視察や、その森で採取したハーブの蒸留体験などを通じて、日本の森の問題やその課題解決に向けた取り組みについて学びを深めました。
子どもたちを引率したコーディネーターらにとっても多くの学びと気付きを得る機会となり、今後の活動に今回の学びが生かされ、CFPがさらに充実した活動となり広がっていくことが期待されます。
2023年
9月
30日
土
2023.09 学校レポート in モンゴル

モンゴル北部オルホン県バヤンウンドル村にある16番小学校は、日本政府の草の根支援により、2017年に新設された学校です。2022年9月に新たに「子供の森」計画に参加。初めての活動では、熟した果実をそのままやジュースで味わうことのできるバードチェリーを植林しました。バードチェリーは果実を乾燥させると、パイやチーズケーキのフィリング、ゼリーにも使うことができるため、非常に汎用性の高いものとなっています。まだ活動が始まったばかりですが、今後は、環境保全についての講義や、樹木の手入れ方法などの実践指導などを行い、少しずつ活動の幅を広げていきたいと考えています。校長であるソルモン先生は「子どもたちがメインである植林プロジェクトを行ったのは初めてでした。子どもたちだけでなく、私たち教員もオイスカのスタッフから植林、管理方法、環境保全について学んでいます。今後もオイスカと協働していきたいです」と期待に満ちたコメントを寄せてくれました。
2023年
9月
30日
土
2023.09 子どもたちからのメッセージ from モンゴル

サエンバエンノー(こんにちは)!
わたしは第15番学校7年生のアヌダリです。これまで環境保全活動に参加したことはありませんでしたが、「子供の森」計画を通して、植林やごみ拾いをしたり、日本の子どもたちとオンラインで交流するチャンスをもらうことができました。環境についてだけでなく、自分の意見を正しく伝える方法や、友達の話を聞くことの大切さなど、多くのことを学びました。
プロジェクトが始まるまでは、私たちの学校には木がありませんでした。しかし、今ではたくさんの木が植えられています。まだ植えられる場所がたくさんあるので、これからも植林を頑張りたいです。また、学校環境をよくするために、ごみ拾いや掃除も頑張っていますが、外からごみが風に飛ばされてくるので困っています。こうした問題が解決できるように、これからも自分たちが植えた木を大切に守り、下級生たちにも環境について教えていきたいと思います。
2023年
9月
30日
土
2023.09 学校レポート1 in インド

植林により涼しい学校環境を
インド北部ハリヤナ州のグルガオンにあるギャン・デヴィ学校は、住宅街に位置しています。緑豊かなキャンパスでは、環境を守るためのルールとして、プラスチックは使用しないことになっています。教員や運営委員会がとても協力的で、「子供の森」計画の全ての活動に積極的に参加してくれています。2022年度には、学校の土壌に合った陰樹としてアショカ、ニーム、ピパル、またマンゴーなどの果樹も植えました。校長であるニーナ・ヤダウ先生は「2005年から定期的に行われている植林活動により、学校とその周辺は、周囲より涼しく、過ごしやすくなっています」と誇らしげに語ってくれました。今後は環境と生態系の保全に対する人々の意識をより一層高めることを目標に、さらに活動を強化していく予定です。
2023年
9月
01日
金
メットライフ生命 支援プロジェクト開始

2023年7月下旬、本プロジェクトが開始したことを記念する植樹活動を3つのサイトでそれぞれ実施。活動前には、プロジェクトに対する学校や地域の理解を深めるため、コーディネーターが各学校を回って説明を重ね、苗木や道具の準備や植林地の整備を、当日を迎えることができました。
2023年
8月
01日
火
2023.08 子どもからのメッセージfrom インド

ナマステ(こんにちは)!
私はインド北部ウッタルプラデシュ州グレーターノイダに住む10年生のアヌです。私は自然から、人生について多くの学びを得ることができました。例えば木や植物は、見返りを求めない愛を教えてくれます。私の地域では、自然のあらゆる部分が神聖であり、有用な種だけでなく、時には危害を受ける危険があるような種(ヘビなど)も崇拝します。朝日を拝むだけでなく、夕日を拝むこともあります。私たちにとって、自然の一つひとつ植物もそのすべてが等しく重要だと思います。
千里の道も一歩からということわざの通りに、私は「子供の森」計画で学んだことを活かして、自分や家族の習慣に小さな変化を起こしました。プラスチック製の買い物袋を麻袋に替える、家の敷地内に小さな庭をつくる、ペットボトルを再利用するなどです。また、学校での植林活動や、環境をテーマにしたディベートや詩のコンテストにも積極的に参加しています。
2023年
7月
31日
月
2023.07 子どもたちからのメッセージ2 from タイ

サワディカー(こんにちは)!
ぼくはスリン県の学校に通う小学1年生のウィンです。ぼくの身の回りには、木、田んぼ、森などの自然がありますが、「子供の森」計画に参加することで、初めて自然を守る活動に参加しました。活動のなかでは、いとこと一緒に水やりをするのが一番楽しいです。これからも植えた木が大きくなるようにお世話をがんばりたいです。たくさんの木を植えて森を育てていきたいと思います。
2023年
7月
31日
月
2023.07 学校レポート1 in ミャンマー

新しく学校菜園にも挑戦
マンダレー地域ピョーボエ郡にあるこの学校では、教員や保護者、村長の「学校を緑にしたい」という気持ちから19年に「子供の森」計画に仲間入りしました。22年度は学校菜園の活動を始めたほか、マンゴー、ジャカランダ、ニームなど150本の苗木を植樹。熱心に管理を続けており、乾燥地にもかかわらず、約90%の木が枯れずに育っています。11年生のアウンさんは、「木を植える活動も野菜づくりも実際にやってみると楽しくて好きになりました。管理を続けたことで、野菜も大きく育って嬉しいです」と笑顔を見せ、今後さらに活動を頑張りたいと意気込みを語ってくれました。
2023年
7月
31日
月
2023.07 学校レポート2 in タイ

豊かな森を目指し管理を継続
タイ東北部スリン県にあるバーンノーントーン学校は幼稚園から小学校までの教育を実施しています。学校は村に入る道の前にあり、近くにノーントーン寺があり、そして広いサトウキビやキャッサバの畑があります。この学校では、サッカーグラウンドの周りや校舎の側など3か所で「子供の森」計画の植林を行ってきました。植林地の管理も継続しており、土壌が悪かった場所でも木が生長しています。
2022年度には植林や木々の管理、環境教育を行いました。木材になる樹種と果樹を一緒に植えて、さまざまな恵みをもたらす森をつくりたい、という学校の意向に沿い、フタバガキ科のヤーンナーや、果樹であるマンゴーやジャックフルーツなどを植えました。学校が掲げている次の目標は、植林地をしっかり管理して学校の森にすること、そして、森の恵みを活かした暮らしについて伝えていくことです。
担当のウッティポン・タウィーポン先生は、「植林地の管理作業に参加する生徒たちは植林地が森の姿へと少しずつ変わっていく様子を見ながら、水やり、施肥、補植等の作業に取り組んでいます。森が空気をきれいにすることを実感したことと、バンコクなど都会では大気汚染などが進み、人の暮らしに害が出るほど環境が悪くなっていることを知って、生徒たちが自分たちのふるさとの森を守って環境を改善しなければという思いを強くしているようです」と話をしてくれました。
2023年
7月
31日
月
2023.07 子どもたちからのメッセージ1 from タイ

サワディカー(こんにちは)!
僕はアユタヤにあるワットラムッド学校のウィンです。木を植えるときは友だちと力を合わせるので、友だちと仲が良くなり、楽しかったです。植えた木は大きかったですが、自分の手で運んで植えられて嬉しかったです(※洪水の多いアユタヤでは、その対策として比較的大きな苗木を植樹)。僕たちが自然を守らなければ、人間を含めた生き物たちが生きづらくなります。そうならないためにも、僕は学校や村の緑の面積がもっと広くなってほしいです。友だちやほかの村の人たちを誘って木を植えていきます。
2023年
7月
31日
月
2023.07 学校レポート1 in タイ

有機農業を学校の外へも広げたい
アユタヤに位置するタコ―ドーンヤーナーン学校は、入り口の前に田んぼが広がっており、田舎特有の落ち着いた雰囲気が感じられます。複数の村から子どもたちが集まる中規模の学校で、近隣住民の方々も明るく友好的です。この学校は「子供の森」計画に対して非常に協力的で、生徒たちが積極的に取り組んでいます。活動初年度である2022年は、植林に加え、有機農業の実習と環境教育活動を行いました。植林したのは、木材として使われるチークやマホガニー、果実を食べられるマンゴーやジャックフルーツなどです。 複数の樹種を植え、豊かな生態系を育むことをねらっています。次年度は、環境にも人にもやさしい有機野菜の栽培を継続し、学校を越えて村にまで有機野菜の栽培が広がるように実施していきたいと考えています。
活動を担当する先生は、『以前より学校がきれいになりました。植えた木を生徒たちがしっかり管理しており、植林や環境教育を通じて、生徒たちが森などの天然資源や環境保全に意識を向けるようになりました。さらに、生徒たちの責任感が強くなったと感じます。「子供の森」計画をきっかけとして、子どもたちには環境保全だけでなく社会貢献ができる人に成長していってほしいです。今後も学校は生徒たちの意識の向上やボランティア精神を育てるための教育活動をおこなっていきます』と意気込みを語ってくれました。
2023年
7月
31日
月
2023.07 子どもたちからのメッセージ from スリランカ

アーユーボーワン(こんにちは!)
僕は、クルネーガラ県にあるクルナワ学校9年生のシトゥンです。「子供の森」計画では、オイスカのスタッフや先生、友だち、地域の人などいろいろな人と一緒に活動できる点が気に入っています。自分の考えをほかの人と比較することができ、多くのことを学ぶこともできるからです。休校期間が延びてしまったり、想定していた時期に雨が降らなかったりと、いくつか問題もありましたが、自然は親の次に僕たちを守ってくれている存在ですから、責任をもって守らなければならないと思い、活動に参加しています。
またオイスカと一緒に学校で野菜づくりの活動を始めてから、自分の家でも野菜を育てています。実は以前にも植えたことがありますが、あまりうまくいきませんでした。今回はオイスカからよく説明を受けて、その通り家でもやって
みました。とてもよく育っています。こうしたチャンスをもらえたことに、とても感謝しています。
2023年
7月
31日
月
2023.07 子どもたちからのメッセージ4 from タイ

サワディーカー(こんにちは)!
ぼくはコンケン県のバーンノーンクンノイ学校のテームです。「子供の森」計画の活動に参加する前は、ゴミ拾いに参加したことはありましたが、植林はしたことがありませんでした。今回活動に参加してみて、友だちと一緒に植林するのが一番楽しかったです。また、木が大きく育っている場所では、聞いたことがない動物の声が聞けてうれしかったです。学校の森がずっとこれからも残ってほしいので、木が切られないように守っていきたいです。
2023年
7月
31日
月
2023.07 学校レポート4 in タイ

森を守る大人になってほしい
ポン学校はコンケン県ポン郡の中心部に位置する中高一貫校教育で、6.4 haの面積を持つ規模の大きな学校です。5棟の校舎とサッカーグラウンド、大きな池があり、植林地も0.96 haあります。2022年は主に植林活動を行いました。木材として活用されるチークや樹脂の取れるヤーンナー、コーヒーなど、合計500本の植林を行いました。植林前の指導、植林地の準備、植林、管理作業などすべての過程に生徒たちを巻き込んで実施しています。「子供の森」計画担当のピライポーン・ルアンルー先生は、「木が増えて学校に森ができたことが一番の変化です。また生徒たちは喜んで活動に参加しているので、植林や環境に対する生徒たちの気持ちがよい方向に向かっていると感じています。今後も、生徒たちが責任をもって植えた木を管理するよう声かけを続けます。森を守る大人に成長していってほしいです。」と語ってくれました。
2023年
7月
31日
月
2023.07 子どもたちからのメッセージ3 from タイ

サワディカー(こんにちは)!
私はチェンライ県にあるバーンパーンオイ学校3 年生のトリーティタヤーです。「子供の森」計画に参加していちばん楽しかったことは、木を植えたことです。オイスカのスタッフに教えてもらいながら、友だちと一緒に100本の苗木を植えました。準備やお世話が大変なこともありますが、「自分の木」ができて誇りに思いますし、新しいことが勉強できたこともうれしかったです。
私たちの村の近くでは、森が伐採されて畑になったり、はげ山になっているところが多くあります。活動の中では、山火事や煙の問題についても教えてもらい、山火事を防ぐための方法を勉強することもできました。これから、もっと学校や地域が木でいっぱいになってほしいです。きれいな花が咲いて、動物たちがすめるような豊かな森ができるように、みんなと一緒にたくさんの木を植えて、化学肥料や農薬を使わずに植物を育てて環境を守っていきたいです。
2023年
7月
31日
月
2023.07 学校レポート3 in タイ

森づくりの最初の一歩
タイ北部チェンライ県にあるバーンターメーウ学校は人里離れた場所にある学校で、道が悪く電気もまだ通っていません。ラーフーという山岳民族が住んでおり、農業で生計を立てていますが、生活に窮する家庭が多くあります。村の水源林や学校の近くにある森が伐採され農地にされたり、はげ山になったりしているところが多いため、「子供の森」計画の活動を通して、子どもたちに木の大切さや森林保全の必要性を伝えることを目指しています。
2022年度には、学校で食べられる果物が実るように、マレーアップル、ランブータン、アボカド、ブルーベリーなどの果樹を中心に100本の苗木を植えました。次の目標は、植林活動のほか環境保全の一環として有機農業、堆肥づくり、ゴミの処理やリサイクル、堰の設置(水の流れを管理するため)などを実施することです。
2023年
7月
26日
水
2023.07 子どもたちからのメッセージ from パプアニューギニア

アピヌン(こんにちは)!
こんにちは、僕は東ニューブリテン州にあるタブタブル小学校 2年生です。友だちにはジェームスと呼ばれています。普段は歩いて通学していますが、ときどきバスを使うこともあります。家族は農業をしているので、僕もよく手伝いをしています。 自分の親しみのある場所に木を植えるのが好きなので、「子供の森」計画の活動にはいつも楽しく参加しています。将来木が大きくなったら涼しい木陰ができたり、木材としていろいろなことに使うこともできて、村の人たちを助けることができると思います。だから一生懸命、友だちと一緒に植林をしました。2022年は雨の降 らない時期がとても長くて、苗木に水やりをするのも大変でした。それでも植えた木が枯れてしまわないように、管理を大切に続けています。未来でもたくさんの人が幸せに暮らせるように、自分のふるさとの環境が少しずつでもよい方に変わってほしいと思っています。
2023年
7月
26日
水
2023.07 学校レポート from パプアニューギニア

子どもたちが楽しんで活動
この学校は、子どもたちに環境を守る意識を持ってほしいという思いから、2022年に「子供の森」計画に参加しました。22年度は、将来的に木材として活用することができるマホガニーを中心に植林しましたが、子どもたちは、木の種類による違いを勉強できたこともおもしろかったようです。 学校の施設整備のため、育った木々を木材として利用することを期待している先生たちも多くいますが、必要に応じて木を切った際には再び植えるというサイクルを大切にするように伝えています。今後は、さまざまな種類の苗木の植林に加えて、学校菜園にも挑戦する予定です。
2023年
7月
02日
日
2023.07 学校レポート1 in インドネシア

他校の見本となるモデルスクールに
東ジャワ州マドゥラ島にある同校は、生徒も教員もみな「子供の森」計画に積極的で、多くの学校から視察に訪れるモデル学校です。2022年度は、マダガスカルアーモンドなどを植栽したほか、学校菜園での野菜づくりを進めました。オイスカからの支援を受けて長年待ちわびていた雨水貯
蔵設備の設置も行い、乾期でも苗木や野菜への水やりに困らなくなりました。担当の先生は、「オイスカの皆さんは、生徒たちが学校内外で環境保全に積極的に取り組めるよう、献身的に働きかけてくれています。環境保全を文化にできるように頑張ります」と意気込みを語ってくれました。
2023年
7月
01日
土
2023.07 子どもからのメッセ―ジ from マレーシア

サラマットゥンガハリ
(こんにちは)!
私はサバ州テノムにあるバトゥティニンカン小学校6年生のヌル ハリシャです。友だちにはカカッと呼ばれています。「子供の森」計画の活動では、自分の木を植えることができ、さらに日本の人たちと知り合って一緒に植樹や文化の交流をすることができるので、とてもうれしいです。以前に日本の人たちと植えた木はもう大きくなって、サワーソップは実をつけるようになりました。パンデミックによって長くこうした交流もできませんでしたが、2022年に久しぶりに日本からお客さんが来てくれました。とても楽しかったです。
「子供の森」計画に参加する前にも、お母さんと一緒に家の庭で華を育てたり、畑をつくって野菜を育てたこともあるので、活動自体に難しいことはありません。私のような学生が自然を好きになることで、たくさんのよい効果があると思います。この活動がマレーシアの多くの学校に広がったらいいなと思います。
2023年
7月
01日
土
2023.07 学校レポート in スリランカ

環境保全活動で学校を盛り上げる
この学校は、スリランカ北西部州のクルネガラ県に位置しており、学校の前には小さな湖があります。多くの地域住民は農業従事者です。以前は一度閉鎖が決定されるほど生徒数が減少していましたが、現校長の献身により、活気を取り戻しています。校長先生によると、「子供の森」計画への参加もこの学校の人気の理由のひとつとなっているそうです。
2022年の植林活動では、マンゴー、グァバ、ザクロ、ネッリといった果樹を中心に植えました。ネッリとは、ビタミンCを多く含む栄養価の高いフルーツです。その他、学校菜園での野菜づくりも行いました。
この学校で英語を担当しているサミタ先生は、「子どもたちは、教室内よりも教室の外で行うプログラムに関心があるのだと思います。また、このプログラムを通じて、木を植えるだけでなく、野菜づくりも行いました。子どもたちが教室の中だけでは学べない知識を深められていると感じています」とコメントしてくれました。
また5年生のサンパスさんは、「木を植えたり、野菜を植えたりするのがとても好きです。おいしい野菜を収穫することができました。また、母にも勧められ、家でも小さな畑をつくり、サツマイモやシカクマメを植えました」と嬉しそうに語ってくれました。
2023年
7月
01日
土
2023.07 学校レポート in インド

薬用樹を中心に植林
南インドでは薬用樹、希少植物、固有植物、絶滅危惧植物の保護・植栽に力をいれており、この学校でも生徒にそれぞれの植物の種類や効能について教えた後、ビャクダン、ニーム、マンゴー等を植えました。ニームの木はインドでは古くから神様から授かった奇跡の木として大切にされ、葉、樹皮、枝、種子などほとんど全ての部位に薬効があるとされています。7年生のジェーバさんは、「薬用植物についての知識や、木々を守ることの価値を知ることができた」とコメントしてくれました。2015年から緑化を続けてきたことで、教員も子どもたちも学校が緑豊かになってきていると感じていますが、まだ緑化が必要な土地も多いため、今後も多くの植物を植えたいと意気込んでいます。
2023年
7月
01日
土
2023.07 子どもたちからのメッセージ2 from ミャンマー

ミンガラパー(こんにちは)!
ぼくはシンターナ学校2年生のアウンです。ぼくにとっての自然は、大きな森があって、いろいろな動物がいる場所です。そこでは動物と人間は友だちで、お互いに助け合って暮らしています。例えば、人間が鳥たちに食べものや隠れる場所をあげるかわりに、鳥はぼくたちに素敵な歌声をプレゼントしてくれます。そのように皆がしあわせでなければいけないと思います。
ぼくが「子供の森」計画の中で一番好きなのは、森林についての勉強です。知らない木や動物についてたくさん勉強することができるし、これからも友だちである動物たちについてもっと知りたいです。今は学校が閉まっているので、学校での活動ができなくて残念です。その代わり、村での植林活動に参加しました。村にたくさん木を植えることで、環境がよくなってほしいと思います。将来は村をよくするために、きちんとごみを処理するグループをつくりたいです。
2023年
7月
01日
土
2023.07 子どもたちからのメッセージ1 from ミャンマー

ミンガラパー(こんにちは)!
私はテインデル学校のヨ―ンです。今は9年生で2019年から「子供の森」計画の活動に参加しています。友だちと一緒に木を植えたり、学校をきれいにするため、清掃活動も行ったりしました。3年間木を植えているので、もう木の植え方を難しいと感じることはありません。緑豊かな場所が好きなので学校に緑が増えてきてとてもよかったです。自分が育てた木が大きくなっていることを見るととてもうれしい気持ちになります。これからも学校がもっと緑に、もっときれいになるように、活動を頑張りたいです。
2023年
6月
30日
金
2023.06 子どもたちからのメッセージ2 from フィリピン

マガンダンハポン(こんにちは)!
僕はパラワン島にあるイスンボ小学校のジェイです。僕たちは、神様が作った自然を守っていく必要があると思います。「子供の森」計画では、木や野菜を植える活動が楽しいです。僕の周りが自然でいっぱいになってほしいですし、野菜のような栄養のある食べ物をたくさん食べたいからです。友だちや先生、家族とも一緒に協力しながら活動しているので、特に困ることはありません。学校や地域のみんながルールを守り、助け合いながら発展してほしいです。そして、大人になったとき、僕もその一員として、社会に貢献していきたいです。
2023年
5月
31日
水
2023.06 子どもからのメッセージ1 from インドネシア

サラマッシアン(こんにちは)!
私は、西ジャワ州スカブミ県にあるスカブミモデル小学校6年生のケイシャです。家でもよく両親の手伝いで植木の水やりをしているのですが、「子供の森」計画では木々の役割や管理について学べるので、両親の役に立つこともできて、楽しく活動しています。植物によって手入れの方法が違うので勉強していておもしろいです。私は、「子供の森」計画を通して友だちと一緒に環境を守りたいという気持ちが強くなりました。みんなが環境に関心を持ち、教室や家をきれいにするよう心がけてほしいと思います。
2023年
5月
31日
水
2023.06 学校レポート in インドネシア

クラブ活動を通して
環境保全の輪を広げる
西ジャワ州スカブミ県にあるこの学校ではYEC(Youth Environmental Club)というクラブ活動として環境に配慮した活動をしています。日本からの留学生がホームステイに訪れることも多く、土地はあまり大きくないですが、「子供の森」計画の活動のおかげで学校の周りは緑に囲まれています。2022年度には植林やリサイクル活動のほか、周囲の小中学校の活動にもサポート役として積極的に参加してくれました。学校内での緑化はすでに完了したため、植林活動では、周辺の道路沿いにマホガニーなどを植えました。今後もエコクラブのメンバーを中心にして、周辺の小中学校などに、これまで取り組んできた環境保全活動を紹介して、活動の輪をさらに広げていきたいと考えています。
先生方は、「オイスカとともに活動を始めて、環境がよりきれいになり、小さな森や東屋ができたことはもちろんありがたいですが、さらに重要な成果として、生徒が普段から環境に配慮した行動をとるようになったことを嬉しく思います」とこれまでの活動の成果について語ってくれました。
2023年
5月
31日
水
2023.06 子どもたちの学校生活 in バングラデシュ

アッサラームアライクム(こんにちは)!
私は山や海、お月様が綺麗な夜や水田など自然が大好きです。純粋な美しさに目が釘付けになってしまいます。「子供の森」計画に参加することで、自然に対して新たな考え方を学ぶことができました。私やクラスメイトは私たちの住むふるさとや周囲の環境が緑の木々で満たされることを望んでいます。学校のキャンパスや国全体がいつの日か以前のように緑で満たされてほしいと強く思っています。
2023年
5月
31日
水
2023.06 学校レポート in バングラデシュ

多様な木の役割を学べるように
この学校のキャンパスは、交通量の多い道路と商業地域に位置しており、樹木がほとんどありません。2022年度の活動として、植林活動に加えて、環境作文コンクール、環境と植樹に関する意識を高めるための短編劇の上演などの環境教育活動も行いました。植樹したのは、家屋や家具を作るのに欠かせないマホガニーや丈夫で風に強いシダー、薬用植物であるミロバラなどです。また、果樹として収益性の高いライチやマンゴーなども植えました。今後は啓発活動にも力を入れ、校内の清掃活動や手洗いなど衛生面に対する意識も高めていく予定です。
この学校の副校長であるバグバリ先生は、「子供の森」計画のプログラムを通して、子どもたちへの木や環境に対する意識の向上を感じているとのこと。子どもたちが樹木の特徴についてたくさんの質問をしてくれるので、さまざまな樹木の役割を教えるようにしていると話してくれました。
2023年
5月
30日
火
2023.06 子どもからのメッセージ from ウズベキスタン

アッサラーム アライクム
(こんにちは)!
僕はマクタブ第54小学校4年生のアガベックです。「子供の森」計画の活動で、友達と一緒に木を植えられて楽しかったです。水を運ぶのも重くなかったし、大変だったことは特にありませんでした。前に家族と一緒に家の畑でりんごの木を植えたことがありましたが、家で植えた時の方が、水が少なく土も固かったです。自然があるときれいなので、緑が増えて欲しいと思っています。植えた木が大きくなるように、水をあげたり、土を柔らかくしたりしてお世話をしていきたいです。
2023年
5月
30日
火
2023.06 学校レポート in ウズベキスタン

砂漠の真ん中で植物を育てる
カラカルパクスタンにあるマクタブ第54学校は、市街地から車で1時間ほどの砂漠の中にあります。周囲には家が10軒ほど並んでいますが、その他は何もありません。校庭にはサッカーコートと畑があり、さまざまな木が植えられています。「子供の森」計画に参加したのは2022年からですが、10年ほど前に水道が通ったことをきっかけに学校独自で木を植え始めました。育った木の木陰にはベンチも設けられ、友達と座って話している子どもたちの様子も見られます。2022年度の活動としては、乾燥地でも育つことのできるサクサウール、桜、桑など130本を植林しました。今後は、日本の小学校とオンラインで交流を行い、環境活動の紹介をするなど、活動の幅を広げていきたいです。
また、この学校には将来、学校の先生になりたいという生徒が非常に多くいます。砂漠に囲まれた学校でありながら、もともと植物を育てる習慣もあることから、将来先生になり、砂漠緑化について次の世代に伝えてくれる人材が育つことを期待しています。
2023年
2月
28日
火
せかい!動物かんきょう会議2023 with モンゴル

今年度の第3回目の「せかい!動物かんきょう会議」として、モンゴルと山口県の小学校の子どもたちがオンラインで交流を行いました。お互いの国について勉強したのち、子どもたちは身近な動物になりきり、身の回りの環境で起きている問題や、人間に気をつけてほしいことなどを発表し合いました。
各プログラムの節目では、自由に質疑応答をする時間が設けられました。お互いの学校生活や知らない動物の生態など、時間内には収まらないほどに、多くの質問が寄せられました。子どもたちは、スタッフによる通訳の力を借りながらも、ジェスチャーを使って表現したり、質問の答え方にも工夫を凝らして交流を楽しみました。
会議の最後には、これからどんな環境を作っていきたいかを発表。モンゴルの子どもたちは、「ゴビ砂漠では植物が少ないので、少しでも砂漠の植物を大切にしていきたい」などとそれぞれの思いを発表してくれました。
2023年
2月
22日
水
学校菜園活動を行っています! in ミャンマー

ミャンマーから学校菜園活動の活動レポートが届いたので紹介させていただきます!今回はチャウマジにある第2研修センター周辺の学校6校で学校菜園活動を行いました。
これまで学校菜園活動を行っていたのは第1センター周辺の学校のみで、第2センターでは初めての活動でした。学校菜園では、その活動を通して、子どもたちが野菜を育てる方法を学ぶことで、自宅でも野菜を育てられるようになります。ミャンマーでは現在、クーデターの影響で生活が困窮する人々が増えており、そのような環境教育への需要が高まっていることを踏まえ、第2センターでも学校菜園活動を行うこととなりました。
菜園で育てたのは空心菜とからし菜といった葉野菜です。鳥に葉が食べられてしまったため、畑の横や上にネットを設置した学校もありました。子どもたちは野菜のお世話を楽しんでおり、学校側としても継続して行っていきたいといっています。
収穫した野菜は、先生が調理を行い子どもたちと一緒に食べました。子どもたちがそれぞれで持ち帰るほどの量はなかったため、高校や中学校では学校菜園活動を拡大していきたいと考えています。
2023年
2月
22日
水
せかい!動物かんきょう会議2023 with インドネシア

2月16日(木)に山口県桜が丘高校とインドネシアの高校生たちをオンラインで結び、今年第2回目となる「せかい!動物かんきょう会議」を開催しました。
キャラクターをつくるため、生徒たちが選んだ動物の中には、インドネシアのコモド島に生息するコモドドラゴンといった地域特有のものや、絶滅の危険性がある動物も見られました。
2023年
2月
15日
水
せかい!動物かんきょう会議2023 with タイ

動物の視点に立ち、身近な環境問題を考えるプログラムである「せかい動物かんきょう会議」。今年度の第1回目は、1月28日にタイと山口県の子どもたちをオンラインでつないで実施。タイからは、アユタヤ県のワットラム学校の子どもたちが参加してくれました。
参加者の自己紹介をしたあとに、まずはお互いの国についてお勉強。その後、子どもたちは身近な動物になりきり、身の回りの環境で起きている問題や、人間に気をつけてほしいことなどを発表し合いました。
2023年
2月
07日
火
植林活動2023 in バングラデシュ

バングラデシュのダッカ近郊の学校で植林活動を行いました。植林活動は計3日間、2023年2月4日にエル・ダラド・モデル学校、2月5日にハッカニア サレヒヤ アリム マドラサ学校、2月7日にニスチントプル デワン エドリッシュ高校で行いました。3校合わせて300本以上が植えられ、樹種としては、生長が早くて丈夫な木材となるマホガニーやチーク、ヒマラヤスギ、鮮やかな赤色の花を咲かせるホウオウボク、実が染料に使われるミロバランの5種が選ばれました。
さらに、ハッカニア サレヒヤ アリム マドラサ学校の植林活動は、地元新聞にも取り上げられました。子どもたちが植林を行うことで、環境保全活動について学ぶことができるとともに、木の世話を通じて子どもたち自身が成長できる、ということが紹介されました。なお同校では1990年代にも「子供の森」計画の活動に参加をしており、当時の子どもたちが植えた木々も立派に育っていることが確認できました。
2023年
1月
31日
火
2019年の植林地でフルーツが実りました in マレーシア

マレーシアのサバ州から植林地の近況報告が届きましたので、紹介させていただきます。
2019年に行った植林ツアーでは、日本からのボランティアも合わせた約80名で、バトゥティニンカン小学校でマンゴーやサワーソップ、ドリアンの植林活動を行いました。約3年が経ち、植林地でモニタリング活動を行ったところ、そこで植えられた木々がすくすくと大きくなっていることが確認できました。サワーソップはフルーツをつけていました!サワーソップは熱帯地域に自生する広葉樹で、フルーツは栄養満点です。当時ツアーに一緒に参加した先生や生徒たちもモニタリングに参加しましたが、実際にフルーツを収穫できたことに満足げな様子でした。
2019年の植林ツアーでは、一緒に木を植えるだけではなく、ソーラン節などの文化交流も行い、子どもたち同士で親睦を深めることができました。
学校にはまだ木を植えるスペースが残っているため、今後もより多くの果樹を植えることを目標に活動を進めていく予定です。
2022年
11月
21日
月
2022 Greeting Card

今年も残すところ僅かとなりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか?
さて、今年も各国からグリーティングカードが届きました!グリーティングカードは、子どもたちが感謝の想いを込めて作ったオリジナルカードで、「子供の森」計画に支援いただいている皆様へお届けしています。カードには子どもたちが植えた木々や毎日触れている風景が描かれており、自然への愛着が伝わってきますね。他の国についても、届き次第こちらのページにアップロード予定です。
来年このカードを受け取ってみたい!という方は、こちらをご覧くだ
2022年
10月
07日
金
2022.8 学校レポート from Malaysia

マレーシアサバ州から8月の活動についての報告が届きました。今回は、ラナウにある、マラナウ小学校の子どもたち27名が、植林活動や、たい肥をつくるための小屋づくりに参加した際の報告です。
2022年
9月
06日
火
学校レポート from Malaysia

マレーシアでの活動が再開しました!
コロナによる活動制限が非常に厳しかったマレーシアにて、5月に活動を再開することができました。久しぶりの活動報告を、ぜひご覧ください!
チーフン小学校の子どもたちがグリーンウェイブ活動の一環として、植林活動とコンポストづくり、リサイクルの勉強会に参加しました。
2022年
8月
29日
月
学校レポート from Thailand

グリーンウェイブ活動を行いました!
タイの子どもたちがグリーンウェイブ活動の一環として、植林活動や環境教育活動に参加しました。
グリーンウェイブ活動とは、国連が定める国際生物多様性の日である5月22日を中心に、世界中の子どもたちが植樹などを行い、生物多様性を理解するきっかけをつくるための活動です。5月22日の各国現地時間午前10時に、子どもたちが植樹する木が地球上を東から西へ波のように広がっていく様子から「緑の波(グリーンウェイブ)」と名付けられました。
2022年
7月
29日
金
2022.7 学校レポート in モンゴル

緑が校舎を彩るように
モンゴル北部オルホン県に位置するこの学校は、ゲルの点在する地域にあり、2015年に建てられた比較的新しい学校で
す。学校が建てられた当初は周囲に緑がなく、「子供の森」計画を通してカエデやライラックなど、これまで250本を超える木々を植栽。子どもたち自身の手で維持管理を行うだけでなく、緑の大切さを伝える環境教育を実施してきました。
2021年度は、給食にも使えるようにと実が食べられるバードチェリー100本の苗木を植えたほか、経済的な理由などでマスクが用意できない生徒200名に手づくりマスクを配布。2015年以来継続してきた活動が評価され、緑化活動に積極的に取り組んだ学校として県から表彰も受けました。同校のガラバダラフ校長先生は、これまでの活動について「校舎しか
なかった学校が、オイスカとの活動によって木々で彩られるようになりとても嬉しい。子どもたちもよく苗木の世話をしている。支援者の皆さまには心から感謝している」と語りました。
2022年
7月
20日
水
2022.7 学校レポート2 in フィリピン

学校から地域へ意識の広がり
ヌエバエシハ州に位置するこの学校は、山に囲まれた環境にあります。コロナの感染拡大を防ぐために、頻繁な外出の規制などが行われました。しかし、計画を立てながら慎重に植林活動を行うことで、ナラの木やサワーソップ、バンレイシを植えることができました。
学校の敷地の近くに木を植えることで、食料を新たに得ることができたり、地域の人たちに環境について意識してもらうきっかけにもなりました。ジャイラ先生は、「木を植えることで子どもたち一人ひとりの環境に対する責任感を育むことができると感じています。コロナ禍にも関わらず、このような植林の機会を作ってくださり、ありがとうございます」と話してくださいました。
2022年
7月
20日
水
2022.7 子どもたちの学校生活3 in フィリピン

マガンダンハポン(こんにちは)!
私の学校生活を紹介します。
コロナが広まったため、レストランに行ったり、学校に行ったり、友達と遊んだりなどの通常通りの生活が出来なくなってしまいました。クラスメイトと一緒に同じ教室で勉強する方が家で課題プリントを行うよりも良いと感じるため、早く対面での授業が再開してほしいです。コロナが収まったら、近くのビーチへ旅行に行きたいです。
2022年
7月
20日
水
2022.7 子どもたちの学校生活2 in フィリピン

マガンダンハポン(こんにちは)!
私の学校生活を紹介します。
私は小学校6年生のバレッテです。以前は毎日学校に行って、教室で先生が話す内容について活発に議論をしていました。今は学校に行くことが出来ず、課題を使って勉強をしています。自分一人ではわからない問題もあるので、そのときは両親に質問しています。先生はコロナ禍でも私たちが勉強できるように、必要なものを一生懸命準備してくれています。コロナが収まったら、学校に行ったり、友だちと遊んだり、川や山に探検に行ったりしたいです。
2022年
7月
20日
水
2022.7 学校レポート3 in フィリピン

マングローブ林が水を浄化
この学校は海岸の近くに位置しており、主な活動としてマングローブ植林を行っています。コロナ禍でも積極的に活動を行い、植林活動だけではなく、保護者へのオリエンテーションや海岸の清掃活動も行いました。マングローブは密に根を張るため、土壌を保持し、川への土壌流出を防ぐことができます。
さらに、6年生のレジ―セルナさんは、「マングローブを植える前と比べると、水質が全く異なります。マングローブによって水が浄化されるのだということを肌で感じました。マングローブは水に含まれている”不純物”を使用して成長したり、蓄えたりしてくれるそうです。きれいな水は地域全体の役に立っています。」と、マングローブによって水質も向上したというお話もしてくれました。
2022年
7月
13日
水
2022.7子どもからのメッセージ from マレーシア

サラマットゥンガハリ
(こんにちは)!
わたしは、サバ州のコタ・ブルー町に住んでいるロッサです。今は学校に登校できるようになりましたが、2021年度はコロナ禍で長い間休校が続いて、友だちにも会えなかったので、すごくさみしかったです。わたしが住んでいる町は、とても景色がきれいで、人もみな優しいです。大好きなふるさとを守るために「子供の森」計
画での植林活動も頑張っています。オイスカの人に教えてもらって木を植えた後、おじいちゃんの畑にもライムの木を植えました。早く大きくなって、実を付けることが楽しみです。
2022年
7月
13日
水
2022.7 学校レポート in マレーシア

ジャックフルーツで
子どもたちに栄養を
この小学校は、マレーシア最高峰のキナバル山を中心とした国立公園から10kmほど離れた渓谷に位置し、児童の多くが、先住民族であるドゥソン族の子どもたちです。こうした山間部の学校ですが、やはり新型コロナの影響は強く、長期間にわたり在宅学習が続きました。学校が再開されても、ソーシャルディスタンスを守った形で授業が行われ、体育など人と接触したり、体を動かすような授業は禁止されました。
2022年
7月
13日
水
2022.7 活動のあゆみとこれから in マレーシア

変化する状況やニーズに
合わせた活動を展開
オイスカが活動を展開するボルネオ島北部のサバ州では、パームヤシのプランテーション開発などにより、熱帯雨林が切り倒され、森林破壊が続いています。こうした問題に対し、オイスカでは学校を拠点に緑化を続けてきましたが、環境教育のニーズが高まる一方、近年は植林できる土地を持たない学校からの参加要請も増えていま
す。
2022年
7月
13日
水
2022.7 子どもからのメッセージ from カンボジア

チョムリアップスオ
(こんにちは)!
6年生のアニザです。コロナで、オンライン授業が続きましたが、接続の問題もあって、あまりうまく勉強できませんでした。やっぱり友だちと一緒に勉強するのが一番です。植林をするのは「子供の森」計画の活動が初めての経験でした。友だちと木を植えて、水やりして木が育っているのを見るのが好きです。
2022年
7月
13日
水
2022.7 学校レポート2 in インド

北インドに位置するWHスミス記念学校は、環境保全活動に力を入れている将来性のある学校です。しかし、学校の敷地の大きさの関係で植林の場所が十分に確保できないため、地域を含めて植林活動を行っています。今年度はコロナ禍で子どもたちが学校に集まれないこともあり、雨水貯留や家での植林など少人数の活動を中心に行いました。7年生のエンジェルヴェルマさんは、「学校に行って友だちと会えるのを心待ちにしています。友だちと一緒に、木を植えたり、ネイチャーツアーに行ったり、絵画コンテストに挑戦したりするのも楽しみです。」と語ってくれました。
2022年
7月
13日
水
2022.7 子どもたちの学校生活2 in インド

ナマステ(こんにちは)!
僕の学校生活を紹介します。
僕はギャンデヴィ学校の5年生です。この学校は北インドのハリヤナ州にあります。コロナの影響で学校は全てオンラインになったので家で勉強をしています。コロナに罹らないために、家にいることが多いです。
僕は自然や緑の環境が好きです。CFPの活動でお気に入りなのは、実際に植林活動を行ったり、木や森について勉強したり、ネイチャーツアーに行ったりすることです。CFPの活動で学んだことを踏まえて、家で苗木をポットに植えたり、屋内での植樹について勉強したりしました。コロナが収まったら、ネイチャーツアーに行って友だちと楽しみたいです。
2022年
7月
13日
水
2022.7 学校レポート in カンボジア

木の成長を見るのがうれしい
ボルブ小学校は、カンボジア東部トボンクムン州にあり、周りには黒コショウの畑が広がっています。環境保全に関心の高かった校長先生は、かねてより農業省に苗木の支援を訴えていましたが、実現には至っていませんでした。そうした中で、他校より「子供の森」計画の話を知り、オイスカに相談したことから、2021年度に植林活動が実現することとなりました。
2022年
7月
13日
水
2022.7 活動のあゆみとこれから in カンボジア

つながりが育む成果
カンボジアでは、研修センターのような拠点はなく、オイスカの訪日研修を受けたOBOGたちが助け合い、「子供の森」計画を推進しています。彼らは、会社員や教員、自営業など本業を抱える傍ら、ふるさとに貢献したいという思いで、各自がそれぞれの地元での調整を担当。活動の際は周辺のOBOGらが応援に駆けつけます。
2022年
7月
06日
水
生徒からのメッセージ from バングラデシュ

アッサラームアライクム
(こんにちは)!
学校が再開しました
新型コロナウイルスの影響で、僕たちの学校も休校になり、長い間登校することができませんでした。その間オンライン授業が続きましたが、インターネットがうまくつながらなかったり、停電の影響を受けたりして、授業に参加できないことがしばしばありました。教室での勉強とはまったく違い、フラストレーションがたまることも多かったです。
学校が再開して、友だちと会うこともでき、勉強できる喜びを改めて感じました。「子供の森」計画の活動もまたみんなと一緒にがんばっていきたいと思っています。
2022年
7月
06日
水
活動のあゆみとこれから in バングラデシュ

住民の生活を災害から守る
バングラデシュでの「子供の森」計画は、現在インド国境に近いクルナ管区を中心に展開。この地域は、ガンジス河によって形成されたデルタに、数千の川や水路、入り江が複雑に入り組む生態系豊かな場所でしたが、開発による環境劣化や、温暖化による海面上昇、塩害、サイクロンの被害が深刻化しており、生物への影響はもとより、住民の生活も脅かされています。
2022年
7月
06日
水
2022.7 学校レポート2 in インドネシア

快適な屋外で勉強
この学校はムラピ山の麓の高原に位置していて、学校のみならず地域の環境保全活動にも熱心に取り組んでいます。シワバゴムノキをはじめとした多くの美しい植物を校庭に植えたことで、景観が本当に大きく変わりました。校舎の裏側にも緑が増えたことで心地の良い場所が増え、子どもたちが屋外で勉強する際の憩いの場となっています。また、ムラピ山の観光博物館の周辺や汚染された川沿いでも植林活動を行いました。観光振興のための周囲の景観の更なる美化や山の水源保全を目的としています。
さらに、各教室の前に花を植えるクラスガーデンの活動や薬草園の活動を導入したことで、学校における植物の種類が豊富になりました。子どもたちは保護者と一緒にこれらの植物のお世話を行っています。植物の水やりや校内清掃活動などのCFPの活動を通して規律を身につけ、学校を卒業した後も地域社会で環境を守るリーダーとして活躍できるような人材を育てていきたいです。
2022年
6月
29日
水
2022.6 子どもたちの学校生活2 in ミャンマー

ミンガラパー(こんにちは)!
私はピョーボエ郡にあるカンティン小学校の4年生です。私の村では、竹を使って帽子やカゴなどを作っています。手作りで作っているので、私の村の誇りだと思っています。元々家で花や木を植えることは好きでしたが、CFPの活動に参加してから、その気持ちがますます強くなりました。コロナ禍が落ち着いたら、大きな果物のなる木を育てて、できた果物をみんなに食べさせたいです。木の下で遊んだり、勉強したり、森の中に遊びに行ったりなど、育った木を使ったアクティビティもたくさん行いたいです。
2022年
6月
29日
水
2022.6 子どもたちの学校生活3 in タイ

サワディカー(こんにちは)!
僕の学校生活を紹介します。
こんにちは!3年生のディーマックです。コロナで、学校で授業が受けられず、今は家で勉強しています。コロナになるのは怖いですが、いつもマスクをしなければいけないのは、大変です。でも、CFPで植林したり、家族でもヒマワリを植えたりして、楽しいこともありました。自分で木を植えたり、環境について学んだことで、自然が好きになったので、コロナが終わったら、友だちと一緒にもっとたくさんの木を植えたり、スリン県で一番大きいフラワーガーデンにも行ってみたいです。
2022年
6月
29日
水
2022.6 子どもたちの学校生活2 in タイ

サワディカー(こんにちは)!
私の学校生活を紹介します。
こんにちは。私はプラーウです。中学2年生です。学校が休みになり、いつも通りに授業が受けられなくなってしまうなど、コロナで私たちの生活も大きな影響を受けました。リモートでも授業を行っていますが、ネットワークなどオンラインの環境がない友だちもいて、みんなが同じように勉強できない状況が続いています。オンラインでの授業は家庭の負担にもなるので、早くコロナが終息し、学校で勉強できるようになってほしいと思います。
2022年
6月
29日
水
2022.6 学校レポート4 in タイ

周囲に再び豊かな自然を
パーンクラーン村、パーントンプン村、パーンアナーケート村の3つの村に接するこの学校は、周囲を森や高い山に囲まれ、山岳民族や各村の子どもたちが一緒に学んでいます。以前は、豊かな自然が見られましたが、人口の増加や農地の拡大のため木が伐られ、はげ山が進行し課題となっています。
2021年度の活動は、マスクの着用や手洗い、校内設備の消毒などコロナ感染防止策を徹底し、学校の敷地内で植林活動や環境教育を実施。ライム、マンゴー、アボカドなど食べられる実のなる樹種や、木材にもなるユカンなど、7樹種100本を植えました。植林には、学校に接する村の住民も参加し、子どもたちのみならず地域の人々の森や環境に対する意識を高める機会ともなりました。
2022年
6月
29日
水
2022.6 学校レポート3 in タイ

地域で育む森づくりの意識
バーンノーンクンノイ学校は、複数の村々に囲まれた小さな学校です。小規模ながらも、校長先生をはじめとする先生方や、村の人々の森づくりへの関心が高く、地域で協力して、子どもたちと活動に取り組んでいます。
2021年度は、新型コロナの影響を受け休校が続き、予定していた植林活動は計画通りの実施とはいきませんでしたが、一部の苗木を、生徒や地域住民へ配布。村の田畑などで植栽するなど、学校と相談の上柔軟に対応し、取り組みを継続しました。
学校や各所に植えられた樹種はパイワーンという竹で、たけのこが学校の給食になったり、販売して収入とすることもできるため、学校の希望により選定されました。現在、配布された苗木は、近隣の住民や子どもたちの手によって、管理が続けられており、学校の植栽地は学校の再開後、すぐに下草刈りを行う予定です。
子どもたちと共に地域でも森づくりを実施したことで、村の住民たちにも自然への意識が高まり、活動の輪が広がりました。
2022年
6月
29日
水
2022.6 学校レポート 2 in タイ

感染防止のため屋外で活動
アユタヤ県では、コロナ禍の影響で、この学校が唯一の活動校となりました。
生徒たちは野菜栽培の手法を学び、教室の外で楽しく活動に取り組むことができました。CFPの活動を通じて、学校の農業活動を継続することができました。
マトーハースィーナー先生は、「CFPに参加することができてとても嬉しく思っています。学校に支援してくださったオイスカの皆さんに大変感謝しております。」とCFPの活動に対して前向きな言葉を述べてくださいました。
2022年
6月
29日
水
2022.6 学校レポート1 in インド

薬草など多様な植物を育てる
小高い丘の上にあるこの学校は、25年前より「子供の森」計画に参加。植林活動を継続してきたため、現在は緑に囲まれています。近年この学校が特に力を入れている活動としてハーブガーデン活動があります。今までに喉や肺の病気に広く使われている薬草を含め、163種の植物を育ててきました。
2021年は、同校でオイスカ活動を推進しているラブグリーンクラブの学生80名が中心となり、風邪の治療に使われる薬草など、約100種類を植え、大切に育てました。活動を通じて子どもたちは、それぞれの薬草が持つ効能や、けがや病気の伝統的な治療方法についても学ぶことができました。「友だちと一緒に活動に参加できて、とてもうれしい。どのように自然を守っていったらよいか、どうすれば自然とともに心豊かに暮らせるかについて学ぶことができた。学んだことを家の庭でもやってみたり、もっと多くの友だちに広めていきたい」と、 サラナさん(8年生)は活動を振り返りました。
2022年
6月
29日
水
活動のあゆみとこれから in インド

子どもたちを地域の皆で育てる
オイスカ南インド総局では、「子供の森」計画(以下、CFP)の推進とあわせ、中・高校生を対象にSALT(Social Awareness & Leadership Training for School Students)というプログラムを実施しています。これは、 学生たちの心身の健全な成長とコミュニティにおけるリーダーシップの力を養うために、地域の有識者に講 師として協力をいただきながら、講義やワークショップを行うものです。参加者の多くは小学生のころよりCFPに参加してきた学生たち。このプログラムを通じて成長した青年たちが地域のリーダーとして後輩たちの指導を行っています。
2022年
6月
29日
水
活動のあゆみとこれから in フィリピン

地元に認められ拡がる取り組み
1991年に「子供の森」計画が産声をあげたフィリピンでは、翌92年より同国政府とCFP実施に関する基本協約を締結。以降も5年ごとに更新し、関係を密にしながら活動を推進してきました。現在は、環境天然資源省、農業省、教育省など3省1局との間で締結しており、環境教育のみならず持続可能な地域づくりへの貢献も期待されています。また、アブラ州では、これまでの取り組みやスタッフの貢献が政府や教 育機関から高く評価され、 同州環境天然資源省と覚書を締結。技術的なサポートと苗木の提供を受けられるようになるなど、 地方においても政府との連携が進んでいます。
2022年
6月
29日
水
2022.6 子どもたちの学校生活1 in インド

ナマステ(こんにちは)!
私の学校生活を紹介します。
わたしの村は、有名な滝が2つもあり、とてもきれいなところです。「子供の森」計画に参加して、オイスカの人から色々教えてもらったり、自然を守り、豊かにしていく活動ができてとても嬉しいです。2020年からコロナで2年間学校が閉まってしまい、ほとんど登校することができませんでしたが、2022年になって、やっと登校できるようになりました。マスクをしたままなのは大変ですが、 友だちと一緒に、植林活動ができることが、嬉しくて仕方ありません。これからも家族や友だちと活動を続けていきたいです。
2022年
6月
29日
水
2022.6 子どもたちの学校生活1 in フィリピン

マガンダンハポン(こんにちは)!
私の学校生活を紹介します。
南イロコス州カブガオに住んでいるレジーです。学校は海のすぐそばにあります。私のふるさとの自慢は、色々な種類の野菜があることと、皆とてもフレンドリーなことです。自然が好きなので、「子供の森」計画の植林活動は楽しみの一つです。2021年にはマ ングローブの植林や浜辺の清掃活動にも参加しました。コロナ禍でずっと学校に行けず、おうちで勉強しなければならなかったので、久しぶりに友だちと一緒に外で活動できていつも以上に楽し かったです。学校が始まったら、ごみの分別も頑張りたいです。
2022年
6月
29日
水
2022.7 学校レポート2 in ミャンマー

乾燥に強い樹種を選定
シンマタウン山から12マイル離れた場所に位置するグエチョー小学校では2007年からCFPの活動に参加しています。活動を始めた当初、村の人々は協力して木を植えましたが、貧しい土壌と水不足のためになかなか強い木が育たないのが現実でした。しかし、村の人たちは緑化をあきらめる様子はなく、植林活動に積極的です。乾燥に強いニームの木を植えることで、学校の豊かな森作りを目指しています。
今年度は学校の他に、家での植林活動にも取り組みました。4年生のリンリンフォーさんは家での植林活動について「初めて自分の家で木を育てることで、木を育てるのは簡単ではないことを実体験から学びました。木の価値について適切に理解することができたと思います。」と語ってくれました。