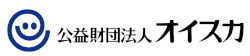トピックス
更新された記事を全て更新順にて紹介しています
2025年
8月
01日
金
2025.08 子どもたちからのメッセージ from タイ

楽しみながら、ごみを分別・再利用しています!
私はアユタヤ県にあるワットーン学校の6年生です。「子供の森」計画では、植林に参加したほか、ごみの分別についても学
びました。活動の中では、ごみの銀行をつくり、分別されたごみをそこで処理・管理するようになりました。家庭でもごみを分別して、学校のごみ銀行に持っていき、換金しています。楽しかったのは、ペットボトルのふたでキーホルダーを作ったことです。捨てられていたものを再び使うことができ、ごみを減らすことにもつながりました。活動に参加して、自分の環境を大切に思う気持ちが強くなったと思います。学校のみんなの環境への意識も変わってきたと感じています。また、ふるさとに木が増えたり、ごみが減ってきれいになったりと、いい変化が生まれていると思います。学校や地域にもっと緑が増え、ごみが少なくなってほしいです。そのためにも、これからもごみを分別し、木を植えていきたいです。
2025年
8月
01日
金
2025.08 学校レポート in タイ

はげ山を繰り返さないために
山岳地帯に位置するこの学校には、山岳民族アカ族の子どもたちが通っています。農業で生計を立てている家庭が多いこの地域では、森林の伐採によって緑豊かだった水源林がはげ山になり、水不足に直面しています。そのため、生徒たちの環境保全への意識を高められるよう、2024年から「子供の森」計画に参加しました。初年度には、実が食べられるものや薬草としても使われるような樹種を中心に植えました。生徒たちがしっかり木の管理を続けているため、植えた木もよく生長しています。今後は森づくりと合わせて、環境に優しい農業の実践指導も始める予定です。
2025年
8月
01日
金
2025.08 子どもたちからのメッセージ from スリランカ

食べられない野菜が無くなりました!
私は、スリランカ・クルネーガラ県にあるタルガムワ学校に通う5年生のネサンディです。「子供の森」計画では、自然や環境についてさまざまなことを学んでいます。これまでの活動では、植林に参加したほか、生ごみや落ち葉など身近なものを使った有機肥料のつくり方や、水やりなど野菜づくりの基礎を教えてもらいました。バケツでの水やりは重くて大変でしたが、その分、野菜が大きく育ち、友だちと一緒に収穫できたときは本当にうれしかったです。以前はナスやピーマンなど、食べられない野菜がたくさんありましたが、自分で育てるようになってから、すべての野菜が好きになりました。今の私にとって、自然はもう一つの学校のような存在です。来年6年生になったら、今の学校を卒業して次の学校に進みますが、そこでも野菜づくりを続けて、育てた野菜を少しでも給食に使えるようにしたいと思っています。
2025年
8月
01日
金
2025.08 学校レポート in スリランカ

学校菜園から地域ぐるみの菜園へ
北西部州クルネーガラ県の農村に位置するクルナワ小学校では、2022年から「子供の森」計画に参加しています。校長先生をはじめ、教員、生徒、保護者が一体となって、限られたスペースを有効に活用しながら、食用や薬用として利用できる樹種の植林や、学校菜園の活動に積極的に取り組んでいます。特に菜園では、昨年よりも広い面積を使って栽培を行い、子どもたちが主体的に作物の世話をする様子が見られるようになりました。活動当初は保護者の参加も少なかったものの、年々関心が高まり、今では地域ぐるみの取り組みへと発展しています。今後は、ワリヤポラ地域のモデルとなる学校菜園を目指し、さらに発展的な活動を進めていく予定です。
2025年
8月
01日
金
2025.08 子どもたちからのメッセージ from フィリピン

自分にできることを、未来のために
ぼくは、南イロコス州にあるカバロアン小学校の6年生です。ぼくにとって自然は、生きものや植物、風や雨など、命を育む大切な存在です。でも最近は、山火事や干ばつ、洪水などが起こり、自然のバランスがくずれてきていると感じます。「子供の森」計画に参加して、さまざまな木の種類や、どうすれば木を上手に育てることができるのかを知ることができました。木を植えたり、お世話をする中で、自然を守る責任や、チームワークの大切さも学びました。植林の時は、硬い土に穴をほるなど大変な作業もありましたが、周りのみんなと協力して頑張ることで乗り越えることができました。木を植えたあと、「この木が何十年も生きて、未来の人たちの役に立つかもしれない」と思うと、少し誇らしい気持ちになります。これからも、学校や地域をもっとよい環境にするために、植林や清掃活動など、自分にできることを続けていきたいです。