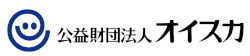モンゴル
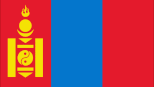
人口:350万人
(2024年4月IMF推計値 日本は1億2,462万人)
一人当たりのGDP:5,668.351US$
(2024年4月IMF試算値 日本は33,805.939US$)
森林率:9.12%(2020年FAO公表値 日本は68.4%)


現地スタッフからのメッセージ
ようやく新型コロナも落ち着き、マスクをつけなくても生活できるようになりました。ただコロナ禍が落ち着き、日常が戻ったように思えますが、経済成長は低調であり、衣料品や食料品などの価格の上昇が続いています。さらに気候変動や砂漠化も進行し、国民へのさらなる影響が懸念される中、政府も10億本の植林キャンペーンを進めるなど緑化を強化しています。こうした中で、「子供の森」計画に期待される役割はますます大きくなっていると感じています。
2022年度は、オルホン県、ブルガン県、ゴビアルタイ県にて植林活動や環境セミナー、日本の学校とのオンライン交流などを行いました。南部のウムヌゴビ県での植林も計画していましたが、天候の問題で、2023年度に持ち越しました。モンゴルでは「木を植えると幸せになれる、長生きできる」という言い伝えがあり、植樹を嫌がる人はいません。
今後も、多くの人と共に、未来を守る活動を続けていきます。
主な取り組み

国全体で進める緑化のひとつに
モンゴルの森林率は、約9%でロシアとの国境沿いに集中しています。その貴重な森も生態系のバランスが崩れ、病虫害などによって危機にさらされています。さらに西南部では沙漠化も進行しており、土地の劣化が進んでいます。こうした問題に対して、政府も気候変動、沙漠化対策に最適な方法は植林であると強調し、2030年までに10億本の植林を行うという全国植樹運動を展開しています。植樹への理解や運動が拡がる中で、「子供の森」計画への参画を希望する学校も増えています。2022年度も多くの学校から希望がありましたが、天候的な問題から植林できる時期が限定されてしまい、植林の実施は4校に留まりました。しかし荒漠化が進むゴビアルタイ県での活動も始まるなど、活動は少しずつ広がっています。2023年には、北部や南部の各地でコロナ前より多くの学校での植林を計画しています。
2021年度植林実績:500本・面積0.25ha
累計(2009年から) 植林9,670本 面積4.65ha
2021年度に植えた主な樹種:エゾノウワミズザクラなど
「子供の森」計画参加学校数:31校(2009年からの累計値)

2023年
9月
30日
土
2023.09 学校レポート in モンゴル

モンゴル北部オルホン県バヤンウンドル村にある16番小学校は、日本政府の草の根支援により、2017年に新設された学校です。2022年9月に新たに「子供の森」計画に参加。初めての活動では、熟した果実をそのままやジュースで味わうことのできるバードチェリーを植林しました。バードチェリーは果実を乾燥させると、パイやチーズケーキのフィリング、ゼリーにも使うことができるため、非常に汎用性の高いものとなっています。まだ活動が始まったばかりですが、今後は、環境保全についての講義や、樹木の手入れ方法などの実践指導などを行い、少しずつ活動の幅を広げていきたいと考えています。校長であるソルモン先生は「子どもたちがメインである植林プロジェクトを行ったのは初めてでした。子どもたちだけでなく、私たち教員もオイスカのスタッフから植林、管理方法、環境保全について学んでいます。今後もオイスカと協働していきたいです」と期待に満ちたコメントを寄せてくれました。
2023年
9月
30日
土
2023.09 子どもたちからのメッセージ from モンゴル

サエンバエンノー(こんにちは)!
わたしは第15番学校7年生のアヌダリです。これまで環境保全活動に参加したことはありませんでしたが、「子供の森」計画を通して、植林やごみ拾いをしたり、日本の子どもたちとオンラインで交流するチャンスをもらうことができました。環境についてだけでなく、自分の意見を正しく伝える方法や、友達の話を聞くことの大切さなど、多くのことを学びました。
プロジェクトが始まるまでは、私たちの学校には木がありませんでした。しかし、今ではたくさんの木が植えられています。まだ植えられる場所がたくさんあるので、これからも植林を頑張りたいです。また、学校環境をよくするために、ごみ拾いや掃除も頑張っていますが、外からごみが風に飛ばされてくるので困っています。こうした問題が解決できるように、これからも自分たちが植えた木を大切に守り、下級生たちにも環境について教えていきたいと思います。
2023年
2月
28日
火
せかい!動物かんきょう会議2023 with モンゴル

今年度の第3回目の「せかい!動物かんきょう会議」として、モンゴルと山口県の小学校の子どもたちがオンラインで交流を行いました。お互いの国について勉強したのち、子どもたちは身近な動物になりきり、身の回りの環境で起きている問題や、人間に気をつけてほしいことなどを発表し合いました。
各プログラムの節目では、自由に質疑応答をする時間が設けられました。お互いの学校生活や知らない動物の生態など、時間内には収まらないほどに、多くの質問が寄せられました。子どもたちは、スタッフによる通訳の力を借りながらも、ジェスチャーを使って表現したり、質問の答え方にも工夫を凝らして交流を楽しみました。
会議の最後には、これからどんな環境を作っていきたいかを発表。モンゴルの子どもたちは、「ゴビ砂漠では植物が少ないので、少しでも砂漠の植物を大切にしていきたい」などとそれぞれの思いを発表してくれました。
2022年
7月
29日
金
2022.7 学校レポート in モンゴル

緑が校舎を彩るように
モンゴル北部オルホン県に位置するこの学校は、ゲルの点在する地域にあり、2015年に建てられた比較的新しい学校で
す。学校が建てられた当初は周囲に緑がなく、「子供の森」計画を通してカエデやライラックなど、これまで250本を超える木々を植栽。子どもたち自身の手で維持管理を行うだけでなく、緑の大切さを伝える環境教育を実施してきました。
2021年度は、給食にも使えるようにと実が食べられるバードチェリー100本の苗木を植えたほか、経済的な理由などでマスクが用意できない生徒200名に手づくりマスクを配布。2015年以来継続してきた活動が評価され、緑化活動に積極的に取り組んだ学校として県から表彰も受けました。同校のガラバダラフ校長先生は、これまでの活動について「校舎しか
なかった学校が、オイスカとの活動によって木々で彩られるようになりとても嬉しい。子どもたちもよく苗木の世話をしている。支援者の皆さまには心から感謝している」と語りました。
2021年
7月
31日
土
2021.7 Mongolia

子ども親善大使OGも頑張ってます!
モンゴル北部に位置するブルガン県・サイハン村にあるこの学校は、2016年から「子供の森」計画に参加しています。以前は、周囲にほとんど木々がありませんでしたが、子どもたちによって植えられた苗木が少しずつ育ち、緑が目立つようになってきました。果樹は実を付け、子どもたちのおやつになっています。
また、同校では、2017年に、モンゴルを代表し、子ども親善大使として日本に訪問したスーギーさんが、帰国後もリーダーとして同校や周囲の学校の活動を牽引してくれています。自分の学校だけでなく、周囲での学校の活動にも、快く手伝いに来てくれる頼もしい存在です。
2019年
11月
30日
土
Green Wave 2019 Report

オイスカが2008年より参画している“グリーンウェイブ”は、国連生物多様性条約事務局(SCBD)が進める取り組みで、5月22日の「国際生物多様性の日」の前後に世界中で行われています。オイスカも「子供の森」計画(以下、CFP)参加校を中心に、国内外でさまざまな活動を実施しました。
2019年
10月
18日
金
2019.10 Mongolia-2

サェン バェノー(こんにちは)
私の1日を紹介します
私はセレンゲ村学校に通う、13歳のホンゴロです。家から学校ま では、歩いて15分ぐらいかかります。ふるさとを流れるセレンゲ川 には、モンゴルで一番長い橋がかかっていて、それがちょっとした 自慢です。
2019年
10月
18日
金
2019.10 Mongolia-1

憩える小さな森をつくるために
セレンゲ村学校は、モンゴル北部・ブルガン県に位置して います。学校には、2haもの広い敷地がありますが、緑はほと んどなく、子どもたちが休める木陰もありませんでした。この拾い敷地を活用して、小さな森を作ることを目的として、2016 年に「子供の森」計画の活動が始まりました。2018年には、アカシアや、バードチェリーなど600本の苗木を植樹。数年経ち 大きく生長した際には、アカシアは強風から子どもたちや校舎を守る防風の役割を果たし、バードチェリーは、栄養価の高い実をつけ、よい給食の食材にもなります。
2018年
5月
18日
金
2018.5 Mongolia-3

サェン バェノー!(こんにちは!)
私の一日を紹介します。
私はサイハン村学校に通う12歳のスーギーです。私の家は学校から50kmほど離れたところにあるので、いつもは寮で暮らしています。「子供の森」計画では、友だちと一緒に植林を頑張りました。
2018年
5月
17日
木
2018.5 Mongolia-2

小さなリーダーが活動を
引っ張っています!
この学校は、ウランバートル市ソンギノハイルハン区にある生徒数1,200名の大きな学校です。この地区はゲル地区とも呼ばれ、周囲には住居用のゲルが立ち並んでいます。
2018年
5月
17日
木
2018.5 Mongolia-1

子どもたちの学習環境を守る
森づくり
バヤンウンドゥル村第4学校は、オルホン県にある初等部から高等部までの子どもたち2,323人が通っている大きな学校です。
2017年
8月
09日
水
Green Wave 2017

世界各地で広がるグリーンウェイブ!
国連生物多様性条約事務局(SCBD)が提唱し、参加を呼びかけているグリーンウェイブは、5月22日の「国際生物多様性の日」の前後(3月1日〜6月30 日)に地球規模で展開されているキャンペ ーンで、地域における緑化などへ青少年の参加を促すものです。オイスカではSCBDと生物多様性の保全活動や啓発を推進するための基本条約を2010年に結び、以来「子供の森」計画(以下、CFP)の参加校を中心に植林活動を行うなど連携した取り組みを行っています。今年も国内外でグリーンウェイブを積極的に実施しました。
2017年
6月
10日
土
2017.6 Mongolia-3

サェン バェノー!(こんにちは)
僕の一日を紹介します。
僕の名前は、バダムサイン・ドゥルグーンです。皆からはドゥルグーノーと呼ばれています。2016年には、「子供の森」計画の親善大使として、日本へ行って日本やミャンマーの子どもたちと一緒に交流をしながら環境について勉強をしました。
2017年
6月
09日
金
2017.6 Mongolia-2

ふるさとを守る森と
子どもを育てるために
セレンゲ村は九州の面積よりも大きいですが、人口は約3400人の田舎の村です。学校から50~300km離れているところから来ている生徒は寮に住んでいるため、長期休みがある時だけ家に帰ります。この地域にはほとんど緑がなく、風が強い時には学校に砂が多く入ってきてしまうという問題がありました。
2017年
6月
08日
木
2017.6 Mongolia-1

砂嵐から学校を守ろう!
この学校は銅鉱山の近くにあります。近年鉱山の開発により森林が伐採されたため、防風や砂防の役目を果たしていた木々がほとんど無くなってしまい、春と秋には強い砂嵐が度々地域を襲うようなりました。2016年はこうした問題に対して、シラカバやモンゴル桜等、合計80本の苗木を学校の周りに植えました。エコクラブを結成して子どもたちが中心になって苗木をしっかりと育てています。また、同校は校内美化にも力を入れており、校内のゴミ拾いを実施しています。
2016年
11月
01日
火
2016.09 CFP Goodwill Ambassadors

9月14日~24日に「子供の森」計画子ども親善大使としてミャンマーとモンゴルから子どもたちを招聘しました!ミャンマーからはアッくん、イーちゃん、モンゴルからはドゥルグーノーくん、スーギーちゃん、ツァツァちゃんが子ども親善大使として来日。各所でそれぞれが取り組む活動の報告をするとともに、同世代の子どもたちや支援者の皆さんとの交流を楽しみました。
2016年
9月
30日
金
2016.9 CFP Ambassadors

ミャンマーとモンゴルの森づくりに参加する子ども代表が来日。報告会を行います!
「自分たちの国の環境を守りたい」、そんな思いで日々「子供の森」計画の活動に取り組む現地の子どもたち、そして現地人スタッフが、各国の環境問題や自分たちが参加している森づくり活動の様子を直接報告します。
2016年
4月
19日
火
2016.April OISCA Mongolia CFP activity#2

2014年に植えた木は今、全て元気に育っています。
この学校は1992年に障害者、孤児やストリートチルドレンのために作った学校です。学生たちは学校で調理実習、食品加工研修、美容技術研修、建築研修、農業と牧畜研修をしています。また、中等教育の勉強をしています。
そして、2014年から「子供の森」計画(以下、CFP)が始まりました。「子供の森」計画では学校の周りと、100km程離れたサマーキャンプ開催地であるトンフェルという村の2箇所にポプラ、ライラック、スグリを植えました。学校の周りに住む人たちもCFP活動に参加してくれていました。2014年に植えた木は今、全て元気に育っています。
2016年
4月
19日
火
2016.April OISCA Mongolia CFP activity#1

オルホン県、第6小学校
この学校は2007年に創立されました。地域の子どもたちは学校に通うために遠くへ行く必要がなくなりました。しかし、学校の周りには何もないため子どもたちには遊べる場所がほとんどありません。
この地域は鉱山地帯であり、さらに強風や嵐が吹くため樹木が育たない環境にあります。そこで、学校の先生たちはオイスカに協力を求めました。こうして、2015年に「子供の森」計画を始めました。子どもたちとその保護者、先生やスタッフたちで中古タイヤを集めてフェンスを作りました。また、トラックで栄養の含んだ土を運び、苗床を準備しました。
2014年
8月
13日
水
Mongol 2014.4

オイスカ研修生OBが活躍
東アジア北部に位置するモンゴルでも、オイスカ研修生OBたちが活躍しています。2013年5月12日、同国の「全国植林の日」に合わせ、エルデネット市の幼稚園、ボガット区の小学校にて、前年に引き続き第2回となる植樹活動を行いました。今回は子どもたちにモンゴルの自然環境や生き物のつながり、植えた木の手入れの方法などを記した教材を新たに独自で作成。学校の子どもたちに配布しました。
まだ試験的で小規模ではありますが、オイスカが育てた青年たちはそれぞれの「ふるさと」で次の世代を育む活動を続けています。
2012年
8月
28日
火
2012.8.28 Mongolia CFP

『モンゴルの大地にて「子供の森」計画進行中』
モンゴル
2010年より「子供の森」計画をスタートさせたモンゴル。少しずつですが、活動はモンゴルの大地にしっかりと根をはってきています。
2012年5月12日、モンゴル国ブルガン県のエルデネト第一幼稚園、ブガット中学校にて「子供の森」計画の植林活動が実施されました。5月12日はモンゴル国の「全国植林の日」で、それに合わせて実施したものです。また、グリーンウェイブの活動としても登録されました(グリーンウェイブ活動の様子はこちらのページをご覧ください)。